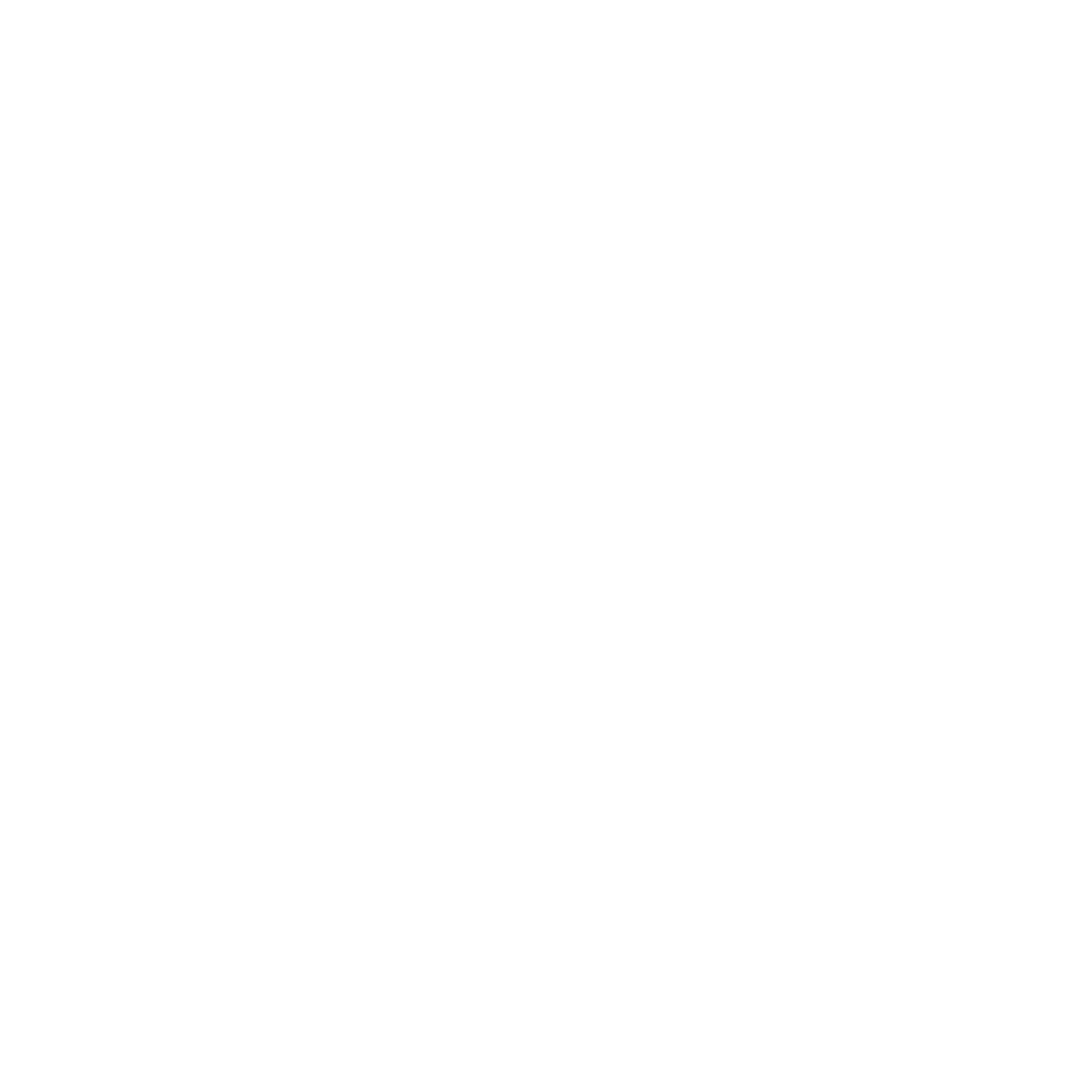ウパニシャッドを実感
山尾三省という詩人がいる。1938年東京・神田に生まれ、早稲田大学西洋哲学科中退。1973年には一年間、インド、ネパールの聖地を巡礼。その後、1977年屋久島に移住。最初の奥さんとの間に3人の子どもを授かり、彼女の死後、二人目の奥さんとの間にも3人の子を授かっている。
深く思索する山尾は、さまざまな本を書き、1995年に『屋久島のウパニシャッド』という本を著している。これは、10代からアートマンという言葉に惹かれ、20代で『ウパニシャッド』と出会った彼が、屋久島にいることで体に刻まれていく、アートマン、そしてブラフマンの実感を綴った本だ。
ウパニシャッドが、必ずしもそれだけというわけではないが、いつでも私の胸の裡にはあった。ウパニシャッドとつぶやけば、なぜとも知らずそこには深い森があり、自分の生をそこに帰することのできる光があることを、感じつづけてきた。(「はじめに」より)
屋久島が教えること
私達にとって『ウパニシャッド』を読んで理解していくのは、なかなか大変だ。しかも、それを実感していくこと、「あー、そうかー」と肚の底から理解するーーというか魂が思い出すというか、そういう状態は、何かの大きな刺激や振動が必要ではないかと思う。
山尾は、聖地の巡礼を経て、屋久島でウパニシャッドと共鳴したのではないだろうか。ここに暮らし、激しい台風に遭い、四季折々の自然の息遣いを見て、人々の生と触れ合う中で、さまざまな言葉を織りなしている。その言葉がウパニシャッドの宇宙観を伝え、読む人を引き込んでいく。
言葉の中にある宇宙
彼の言葉は、とても繊細に選ばれていると思う。一語に込められている意味、読み方は、同じ言葉でも文章によっても使い分けられている。それは、再三、言葉が重要だとウパニシャッドに書かれていると告げていることからもわかる。少し長いが、引用させてもらおう。
たとえば、「語は火に帰入する」という断言。これは各ウパニシャッドに共通な理解事項のひとつなのであるが、人間の言葉というものは火から生まれた。チャーンドーギァ・ウパニシャッドのウッダーラカ・アールニの説において見てきたように、人間が死ぬ時には、その語(言葉)は意に入り、意は気息に入り、気息は火に入り、その火が最高神として実在に帰入して終わる。
火と語は論理的に何の関係もないようなものであるが、「人が死ぬとその語は火に帰す」と断言されると、にわかに、人の語とは火であり、火とは人の語の遠い遠い始まりであったのだと、了解されてくるものがある。人間が初めて火を焚いた時に、そこに同時に人間の言葉があった。今私が五右衛門風呂の火を焚く時も、その振動とともにそこに私の原初の言葉がある。さらに遡るなら、まだ太陽系はなく太陽だけが燃えていた時、すでにそこには人の言葉の原初が燃えていたのでもあろうか。(「第六章 眼は、人における太陽」より)
アートマンである自分
山尾の視点は気候に、樹木に、海に、1本の木に、岩に、野菜に、小鳥に、街の人達に、子ども達に、なくなった先妻の魂に、さまざまに移りながら屋久島とウパニシャッドとを語っていく。自分自身のこと、自分がアートマンであること、アートマンとブラフマンの関係は、屋久島にいることで深く深く了解されていくのだという。
ウパニシャッドという森は、私の住んでいる屋久島の森と同様に、目の前に在る。というより、その中に住んでいるといった方が適切かもしれない。古典が古典としてのみ与えられるのではなく、今の風景として与えられるのは、三千年前の生死(しょうじ)も今の生死もともに生死であるという自明の事実に基づいているからであり、そこに出遇いさえすれば、いかなる古典も古典という深みを秘めたままに現代思想となる。(「あとがき」より)
端から端まで丁寧に時間をかけて読むことで、じわじわと、ずぶずぶと深く胸の裡にのめり込んでいくような一冊。正直言って、感動した言葉を書き出していったら、一冊まるごとの写本になってしまうかもしれない。
この本の持つエネルギー、トーンで読めば、ウパニシャッドがわかりやすくなるような気がする。なんというか、より瞑想的に読めそうな気もする。
山尾は2001年になくなった。彼はもう新しい言葉は紡がないけれど、この出遇いによってウパニシャッドへの理解を深めてくれたことに感謝したい。彼の詩の、彼の感性の、彼の感受性の一つひとつにもっと触れたいと思う本だ。