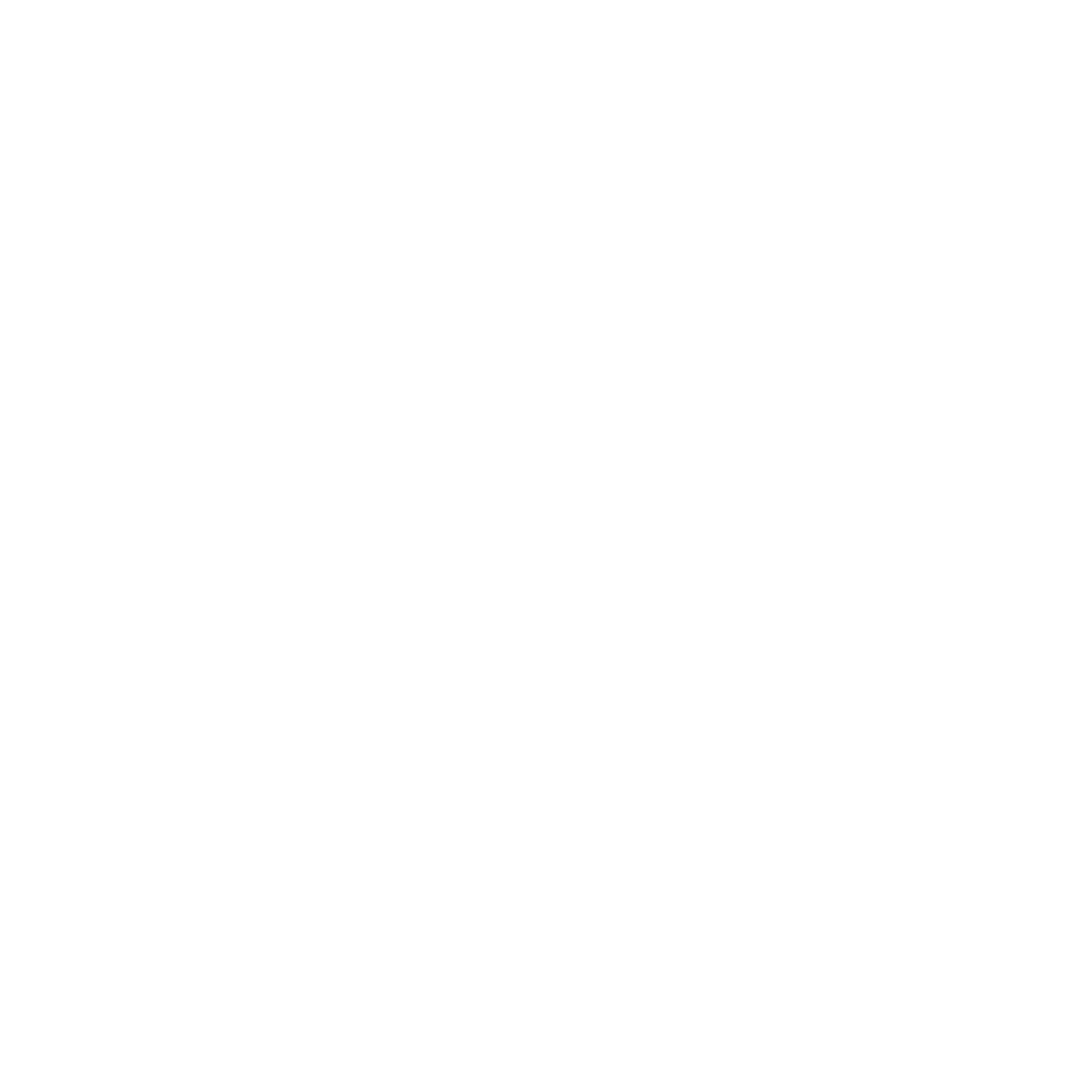こんにちは、丘紫真璃です。今回は、このコラムで、もうすでに登場しているスウェーデンの児童文学作家リンドグレーンの作品を再び取り上げたいと思います。
のびのびと自然体の子ども達を描かせたら、リンドグレーンの右に出る作家はいないのではないかと思うくらい、リンドグレーンの描く子ども達は、とにかく魅力的な子ばかりです。読者は自然と、登場人物の子どもが好きになってしまい、その子の運命がどうなるのかと、ページをめくる手が止まらなくなってしまいます。
そんな名作を数多く世の中に送り出したリンドグレーンですが、今回は『さすらいの孤児ラスムス』をみなさんと見ていきたいと思います。
さすらいの孤児ラスムスとは
『さすらいの孤児ラスムス』は、1956年にスウェーデンの児童文学作家アストリッド・リンドグレーンが出版した児童書です。リンドグレーンは、ラスムスという名前の少年が登場する作品を三つも書いていますが、このラスムス君は、9歳の少年で、孤児の家で暮らしています。
この『さすらいの孤児ラスムス』で、リンドグレーンは、1957年に「国際アンデルセン賞」を受けました。名作は何度読んでも、新鮮に感動できるものですが、『さすらいの孤児ラスムス』こそは、あきるほど読んでもあきることのない、何度でも感動できる名作です。
自分で親を探しにいく

主人公のラスムスは9歳。ヴェステルハーガの孤児の家に物心ついた時からずっと暮らしています。元気な少年なのですが、もちろん、孤児の家に住むどの子も考えているように、ラスムスもまた、よその家にもらわれていきたいと、いつもそう望んでいます。
子どもたちのうちのだれかが、よその家にもらわれていく、ということは、なにものにもくらべることのできないことであった。そういう幸福を夢に見ない子どもは、このヴェステルハーガの孤児の家には、ひとりもいなかった。(略)
とにかくじぶんをもらっていきたい、というひとが、いつの日にかはやってくるはずだ、という希望をすてることができなかった。下男や女中としてこき使うためではなく、ほんとうの家の子どもとしてもらいたいというひとが。
里親をもつこと、それは孤児の家のこどもたちが、この世のなかで考えられる最大の幸福なのであった
(『さすらいの孤児ラスムス 第1章』)
そんな孤児の家に、ある日、里子をもらいたいというお金持ちの商人ときれいなおくさんがやってきます。何とか目にとまりたいとはりきったラスムスは、はりきりすぎたあまり空回りばかりしてしまい、孤児の家の院長ヒョーク先生に水をぶっかけてしまったりと、みじめな失敗を繰り返します。
結局、商人夫妻が連れて帰ったのは、ちぢれ毛の女の子でした。
本当は、ラスムスはよく知っていたのです。もらわれるのは、いつも、ちぢれ毛の女の子ばかりで、ラスムスのような針毛の男の子には、ほとんどもらわれるチャンスはないということを。ラスムスは、商人夫妻と女の子が馬車で去っていってしまった後、こう考えます。
それでも、この世界のどこかには、針毛の男の子がほしいというひともいる、ということはまったくありえないことでもないだろう。
だれか、ただひとりでも…どこかに…あの道の曲がり角のずっとむこうに
(『さすらいの孤児ラスムス第3章』)
ラスムスは、親友のグンナルに、孤児の家から一緒に逃げ出して、自分達で親を探そうと持ちかけます。けれども、グンナルはそんなことはできるわけないと相手にしません。
ラスムスも弱気になりかけますが、ヒョーク先生に水をぶっかけてしまった罰として、明日の朝、鞭うたれることになっていたことを思い出し、やっぱり逃げてしまおうと心に決めます。そして、真夜中に一人孤児の家を抜け出すのです。
心優しい風来坊オスカル
ラスムスは、暗闇と一人ぼっちの恐ろしさでブルブル震えながらどんどん走り、乾草がたくさん積まれた納屋を見つけて転がりこみ、眠りこんでしまいます。
すると、その納屋の中の乾草にうずもれて、ラスムスと同じように眠りこんでいる男がいたのです!ラスムスが目をさますと、知らない男が乾草から突然、顔を突き出してきたので、ラスムスはびっくりしてしまいます。
乾草のかたまりのうしろに、顔がにゅうっとあらわれた。ひげもそらない、黒いひげづらのまるい顔だった。ふたつのぱちぱちする細い目が、びっくりしたようにラスムスをながめ、まるい顔がくずれるように、にっこり笑った。
この見も知らぬ男は、べつにこわそうでもなかった。そして、男はくすっくすっと笑い出して、声をかけた
(『さすらいの孤児ラスムス』第4章)
これが、ラスムスと風来坊のオスカルの出会いでした。オスカルはすりきれた上着にずた袋のようなズボンというみずぼらしい服を着ていましたが、優しく面白い人でした。家を持たずに歩き回って旅をしながら暮らしているらしいのです。
ラスムスは、すぐにオスカルと仲良くなります。そして、孤児の家を逃げ出したものの、この先一人でどうしたらいいのか途方にくれていたラスムスは、オスカルに、自分の里親が見つかるまででいいから、一緒に旅に連れて行ってくれるように懸命に頼みます。
スウェーデンの夏の街道をリュック一つ背負ったオスカルと、無邪気なラスムスとがブラブラと歩いて旅する様子は、のどかな詩のように美しく描かれます。二人は、昼日中だろうが夜だろうが気がむいた時にいつでも眠ったり食べたりして、自由気ままに過ごします。
孤児の家でヒョーク先生に怒られながら規則の中で生きてきたラスムスは、すぐに風来坊の生活が気に入り、里親を見つけることは少しも急ぐことはない…と思いはじめます。
ところが、楽しい事ばかりではありません。二人はヒョンな拍子から宝石強盗の現場を目撃してしまい、強盗達から宝石を取り返したり、命を狙われて追いかけられたりと息のつまるような大冒険を繰り広げます。
オスカルが強盗事件の容疑者と間違って警察に捕まったりと波乱の展開が続きますが、ラスムスは機転をきかせてオスカルを助け、とうとう、宝石強盗を捕まえるという大手柄を立てるのです。
ラスムスの本当のわが家
警察署長は、大手柄のラスムスをほめてくれますが、だからといって、孤児の家から逃げ出したことを大目に見てくれるわけではありませんでした。孤児の家に返そうとした署長さんを振り切って、ラスムスは、走って逃げまくります。
オスカルは、そんなラスムスを捕まえて、大きな農場を持つ、親切そうなお百姓さん夫婦のうちに、ラスムスを連れていきます。この夫婦は、ちょうど農場の世話をしてくれる跡継ぎの男の子を探していて、ラスムスに養子にならないかと尋ねます。
それはもうラスムスにとって、夢のような話でした!だって、ラスムスはお金持ちで、きれいなお父さんとお母さんが欲しいとずっと願い続けてきたのです。ラスムスは天にものぼる心地になって、すぐにOKしました。
それなのに同時にラスムスは、胸が針でさされたような気持ちになったのです。このうちの子どもになるということは、オスカルと別れなければならないということだったからです。
次第に去っていくオスカルの姿を見て、ラスムスは悲しくてたまらなくなり、どうにも我慢ができなくなって無我夢中で追いかけます。そして、オスカルに自分のパパになってくれるように頼みます。
オスカルは風来坊のパパなんてあるか、と怒ったように言うのですが、ラスムスはあきらめません。立派な農場できれいでお金持ちのお父さんとお母さんと暮らすよりも、オスカルといっしょに歩く方がいいというのです。冬に歩き回っていれば足の爪がさけるかもしれないけれど、それでもいいと言いはります。
「歩きまわってれば、そんなにたくさん、お金はいらないよ」
ラスムスは口ごもるようにいった。
「冬になって足の爪がさけたってかまわないよ。やっぱりオスカルといっしょに歩くんだ。やさしいオスカルだもの。やさしい……」
ラスムスはことばがつづけられなくなり、また、わっと泣き出した」
(『さすらいの孤児ラスムス』第14章)
とうとうオスカルは、ラスムスの好きにしな、と優しく言ってくれました。こうして、ラスムスは、立派な農場を後にして、オスカルと旅を続けることになったのです。大満足で歩くラスムスを見て、オスカルは不意に言います。
「おれもおまえといっしょにいたいんだぜ」
(『さすらいの孤児ラスムス』第14章)
最後にオスカルは、荒れた柵に囲まれた小さな小屋に、ラスムスを連れていきます。そこは何と、オスカルの家でした! そして、そこには、オスカルのおかみさんまでいたのです。ラスムスは、オスカルにおかみさんと家があったことに仰天します。
おかみさんのマルチーナは、オスカルが突然、ラスムスを連れ帰ってきたことに戸惑いながらも、「あたしたちの家に住みたいかい?」と、ラスムスに聞いてくれます。

すると、ラスムスはふいに、それこそまさにじぶんが願っていたことだ、という気がした。湖のほとりのこの小さいうすぎたない家に、オスカルとマルチーナといっしょに住みたいと思った。
オスカルとマルチーナは、きれいでもないしお金持ちでもなかった。マルチーナは、羽根のついた空色の帽子をかぶっていなかったが、そんなことはどうでもよかった。ここに住みたかった。
「じゃ、マルチーナおばさんは針毛の子でいいの?」ラスムスは、はずかしそうにたずねた
(『さすらいの孤児ラスムス』第14章)
マルチーナは、ラスムスをしっかりと抱きしめてくれました。こうして、ラスムスが、本当のわが家を見つけたところで、幸せいっぱいに物語はエンディングを迎えます。
ラスムスが、お金持ちの夫婦よりも風来坊のオスカルを選んだわけは、子どもらしい純真な目でオスカルを見ていたからなのでしょう。限りなくサットヴァに近い、晴れた日の湖のように澄み切った目でオスカルを見ていたからこそ、本当のオスカルの姿を見ることができたのだと思うのです。
浮浪者だとか、みずぼらしい恰好をしているなどといううわべの見かけにだまされず、ラスムスは、オスカルの心の綺麗さをちゃんと見ぬいていたのでしょう。
何でも持っているお金持ちのお百姓さんの家の子にならなくてよかったのかと聞くオスカルにラスムスは答えます。
こうやって歩いていると、目に見えるもの、みんなじぶんたちのものだって、考えてたんだよ。(略)
シラカバもみんな、ぼくらのもの。湖水も、野原も、フウリンソウもみんなぼくらのもの。道も水たまりも、ぼくらのもんだよ
(『さすらいの孤児ラスムス 第14章』)
こう言って、陽気に飛び跳ねて、心の底から満ち足りているラスムスは、9歳ながらすでに、ヨギーの資質を十分に持っているといえないでしょうか。いや、逆に大人の私達が失ってしまった純真なものをラスムスは持っているといえるのだと思うのです。
そして、それこそが、私達がヨガでもう一度取り戻したいものなのでしょう。
児童文学のすばらしい点の一つはページを開けば、そういった子どもの純真さを味わうことができることにあると私は思います。スリル満点、ユーモアたっぷり、おまけに感動の涙を流せること受けあいの『さすらいの孤児ラスムス』を、みなさんもぜひ読んでみて下さい。
参考資料
- 『さすらいの孤児ラスムス(1965年)』アストリッド・リンドグレーン著 尾崎貴義訳(岩波書店)





















![福田真理×MIKIZO YouTube LIVE[アーユルヴェーダの先にあるもの]](https://i.ytimg.com/vi/rY5WcQmR9EI/mqdefault.jpg)

![「腰椎ヘルニア」にヨガ・ピラティスでできること。リハビリの現場では何をしている?理学療法士:間所昌嗣先生にお話しいただきました[ スポーツ医学アカデミー2025 ]](https://i.ytimg.com/vi/lc7O54fyEus/mqdefault.jpg)