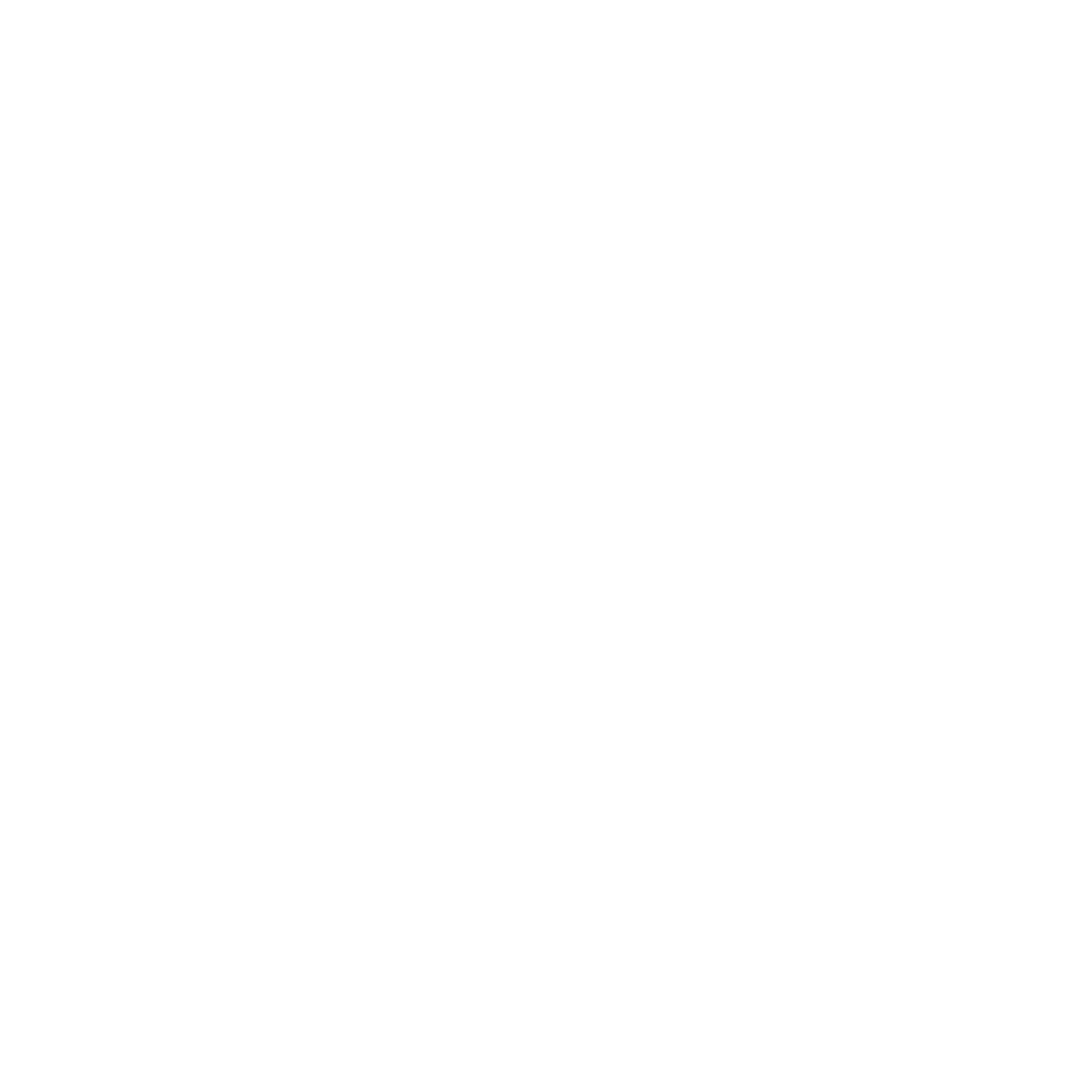こんにちは!丘紫真璃です。今回は『アイヌ神謡集』を取り上げたいと思います。
その題名の通り、アイヌの伝統的な謡「カムイユカラ」が13編おさめられているものなのですが、一度は開いてみたことがあるという方も、けっこういらっしゃるのではないでしょうか。
19歳という若さで亡くなったアイヌの少女、知里幸恵の手で書かれたもので、日本語とアイヌ語が非常に堪能だった彼女は、文字を持たないアイヌ語をローマ字で表記し、その横に美しい日本語訳をつけました。
彼女の美しい日本語訳を読むと、アイヌの人々のカムイユカラの美しさがほんの少しのぞけるような…そんな気が私はします。
ところで、ここまで読んで、このコラムは、ヨガのコラムであって、アイヌのコラムではなかったような…と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、アイヌの世界観とヨガの世界観は、深くつながるところがあるように私は思うのです。
そんなわけで、『アイヌ神謡集』を手がかりに、アイヌの世界をたずねてみることにいたしましょう。
19歳でこの世を去った語学の天才・知里幸恵さん
『アイヌ神謡集』を手がけた知里幸恵は、1903年6月8日、北海道の登別川のほとりに生まれました。
6歳の時、旭川市に住んでいた叔母、金成マツの養女になります。マツと、マツの母親(幸恵の祖母)は、カムイユカラの謡い手でした。幸恵は、叔母や祖母のカムイユカラを毎晩聞いて育ちます。
一方、学校では日本語で授業を受けました。成績はバツグンだったらしく、旭川市の実業学校にもただ一人のアイヌの乙女として入学します。しかも、入学試験の成績が110名中4番だったというのですから、相当、頭脳明晰だったことがうかがえますよね。
そんな幸恵は15歳の時、アイヌ語研究をしていた金田一京助に出会います。金田一京助は、その当時、急速な勢いで失われつつあったアイヌ語や、アイヌ文化を残す重要性を、熱心に幸恵に伝えました。京助に影響され、幸恵はカムイユカラをローマ字でノートに書き記すことをはじめます。
そうして書きためたものを『アイヌ神謡集』として出版すべく、幸恵は熱心に準備を進めていたのですが、『アイヌ神謡集』の原稿の最後の手直しをした数時間後、持病の心臓の発作で、惜しくも亡くなってしまいました。
しかし、彼女の『アイヌ神謡集』は、自分達の文化に自信を失っていたアイヌの人々が、自信と誇りを取り戻すきっかけにもなりました。『アイヌ神謡集』に励まされて、数々のアイヌ民族の人々が、アイヌ文化を残す運動に立ち上がったのです。
彼女の『アイヌ神謡集』がなかったら、今、アイヌ語はこの世から消滅していたかもしれません。そしてまた、私達がここまで深く、アイヌの文化を知ることもできなかったことでしょう。
フクロウの神のカムイユカラ「コンクワ」
アイヌ神謡集の序文は、次のようにはじまります。
その昔この広い北海道は、私たち先祖の自由の天地でありました。天真爛漫な稚児の様に美しい大自然に抱擁されてのんびりと楽しく生活していた彼等は、真に自然の寵児、なんという幸福な人だちであったでしょう
ー『アイヌ神謡集』より
北海道を訪れた事がある方は、あの雄大な大自然を思い浮かべてみてください。あの広大な大自然の中、アイヌの人々は狩りをし、漁をして暮らしを立てていたのです。

アイヌ神謡集の序文に、その様子が鮮やかに描かれます。
冬の陸には林野をおおう深雪を蹴って、天地を凍らす寒気をものともせず山又山をふみ越えて熊を狩り、夏の海には涼風泳ぐみどりの波、白い鷗の歌を共に木の葉のような小舟を浮べてひねもす魚を漁り、花咲く春は軟らかな陽の光を浴びて、永久に囀る小鳥と共に歌い暮して蕗とり蓬摘み、紅葉の秋は野分に穂揃うすすきをわけて、宵まで鮭とる篝も消え、谷間に友呼ぶ鹿の音を外に、円かな月に夢を結ぶ、嗚呼なんという楽しい生活でしょう
ー『アイヌ神謡集』より
そんな大自然に囲まれた楽しい暮らしをしていたアイヌの人々の謡「カムイユカラ」が、この本にはおさめられているというわけです。
カムイユカラは、フクロウ、キツネ、ウサギ、クマ、カエル、沼貝、あるいは、雷や、風や、火の神様といった様々な神様が一人称で語るという形式をとっています。面白い謡がたくさんあるのですが、ここでは、梟の神様が一人称で語る「梟の神が自ら歌った謡・コンクワ」をご紹介しましょう。
この梟の神は、シマフクロウのことなんだそうです。昔の北海道にはシマフクロウがたくさん生息しており、シマフクロウは、人間の国を見守る神様だとアイヌの人々は考えてきました。
その人間の国を見守る神様である梟がある日、人間の世界が飢饉であることを知り、それはなぜかと原因を探ります。そして、それは天国にいる魚を司る神様と、鹿を司る神様のせいだということをつきとめます。 梟の神様は、次のように歌います。
人間の世界に飢饉があって人間たちは今にも餓死しようとしている。どういう訳かと見ると天国に鹿を司る神様と魚を司る神様とが相談して鹿も出さず魚も出さぬことにしたからであったので、(略)人間たちは猟に山に行っても鹿も無い、魚漁に川に行っても魚も無い
ー『アイヌ神謡集』より
人間の世界が飢饉になったわけが、天国にいる鹿を司る神様や、魚を司る神様が、鹿や魚を出さないことにしたからだ、という表現は独特ですね。
鹿を司る神様が出す鹿とは、自分の分身のことなんだそうです。山を走る鹿の一匹一匹は全て、鹿の神様の分身なのですね。同じように、川を泳ぐ魚の一匹一匹も全て、魚の神様の分身なわけです。
ところで、なぜ、鹿や魚の神様が、自分の分身である鹿や魚を人間達に出してやるのをやめたのかといえば、それは、人間達の行いが悪かったせいでした。人間達が、山で捕った鹿や、川で捕った魚を粗末に扱ったというのです。
天国の鹿の神や魚の神が、今日まで鹿を出さず魚を出さなかった理由は、
人間たちが鹿を捕る時に木で鹿の頭をたたき、
皮を剥ぐ鹿の頭をそのまま山の木原に捨て置き、
魚をとると腐れ木で魚の頭をたたいて殺すので、
鹿どもは、裸で泣きながら、鹿の神の許へ帰り、
魚どもは、腐れ木をくわえて魚の神の許へ帰る。
鹿の神、魚の神は怒って相談し、鹿を出さず、魚を出さなかったのであったー『アイヌ神謡集』より
しかし、人間達が鹿や魚をていねいに取り扱うならば、鹿や魚を出してやろうと、神様たちはつけくわえます。
梟の神は、眠っている人間の夢の中に出ていき、鹿の神、魚の神の言葉を伝えます。すると、人間達は自分達が悪かったと反省し、鹿や魚をていねいに扱うようになります。
魚をとる道具を美しく作り、それで魚をとる
鹿をとったときは 鹿の頭もきれいに飾って祭る
それで魚たちは、よろこんで美しい御幣をくわえて魚の神のもとに行き、
鹿たちは、よろこんで新しく月代をして鹿の神のもとに立ち帰る。
それを鹿の神や魚の神はよろこんで、沢山、魚を出し、沢山、鹿を出したー『アイヌ神謡集』より
こうして人間たちがひもじい事もなく暮らすようになったので、私も安心しました…と梟の神は物語りました…といった具合に、このカムイユカラはしめくくられます。
古代の世界には神様が身近を取り巻いていた

このカムイユカラを見ただけでも、パタンジャリの教えと非常につながるものがあるように、みなさんは思いませんか。
このカムイユカラに出てくる魚とは、サケのことです。川を下ってくるサケは全て、神様の分身だったわけですよね。実際、アイヌの人々は、神様の魚が下ってくる川を綺麗に汚さないようにし、神様の魚を非常にていねいに取り扱っていたということです。
決してとりすぎないように一回の漁で一匹しかとらず、とった魚は骨まで大事に使い切りました。その欲張らず、敬虔(けいけん)な生き方は、ヨギーの生き方そのものともいえますよね。
それもそのはず、アイヌの世界観とヨガの世界観は、どこか通じるものがあるのです。
アイヌの人々にとって、川を泳ぐサケの一匹一匹は全て、神様の分身でした。神様の分身…つまり、神様そのものといえますよね。
山を走る鹿の一匹一匹も全て神様であるし、森をうろつくクマも全ては神様でした。ありとあらゆる動物や、植物は全て、神様だったのです。そしてまた、火や雷や風といった自然現象の中にも神様は宿っていると考えられましたし、船や錨といった物の中にまで神様はいると、考えられていたのです。
全てのものには神様がいる…。
その考え方は、ヨガと同じですよね。ヨガでもまた、ありとあらゆる全てのものは神なのだと考えます。
アイヌの人々にとっても、古代インドの人々にとっても、暮らしのすぐそばに、神様はとりまいていたのです。アイヌの人々はカムイユカラを日々の暮らしの中で口ずさみ、古代インドの人々は、オームを繰り返し唱え、いつだってどこにだって、まわりの全ての中に神様がいるということは、もう魂の中に刻み込まれていたのです。
アイヌやインドだけではありません。私達の日本にもまた、森羅万象の全てのものに神様が宿っているというアニミズムの考え方がありました。世界じゅう見回しても、そうした考え方は決して珍しくはなく、古代の世界のあちこちに見られます。
古代の地球の中には、神様は当たり前に身近に存在していたのです。そして、神様が身近に存在している時、人はもう自然に、感謝と祈りの謙虚な暮らしを、まるで息をするように自然に繰り返していたのです。
神様がそっと戻ってきてくれる時
けれども、今、現代に生きる私達は、古代の人々が自然に持っていた、まわりの全てに神様がいるという考え方を失ってしまいました。
『アイヌ神謡集』の序文でも、次のように書かれています。
太古ながらの自然の姿も何時の間にか影薄れて、野辺に山辺に嬉々として暮していた多くの民の行方も亦いずこ。僅かに残る私たち同族は、進みゆく世のさまにただ驚きの眼をみはるばかり。しかもその眼からは一挙一動宗教的感念に支配されていた昔の人の美しい魂の輝きは失われて、不安に充ち不平に燃え、鈍りくらんで行手も見わかず、よそのご慈悲にすがらねばならぬ、あさましい姿、おお亡びゆくもの…それは今の私たちの名、なんという悲しい名前を私たちは持っているのでしょう
ー『アイヌ神謡集』より
日本人がアイヌの人々の土地を侵略して、北海道という名前をつけ、アイヌ語やアイヌ文化を禁じた時、アイヌの人々の暮らしの中から、カムイユカラは失われてしまいました。
それと同時に、人々の暮らしの中から、神様が消えてしまったのです。感謝と祈りのヨギー的な幸福な暮らしはなくなってしまったのです。
森羅万象の全てに神様がいると信じていた日本人だって、いつしか、そうした考え方を失ってしまいました。私達が生まれた文明社会の中にはもう、身近に神様は存在していません。
けれども、それでも私達のDNAの中には、アニミズムが組み込まれているのです。だからこそ『アイヌ神謡集』を開いた時、なつかしいような気持ちがするのでしょう。
19歳のアイヌの乙女、知里幸恵が残した『アイヌ神謡集』こそは、私達が遠い昔に失ってしまった大切なものを呼び起こしてくれる一冊だといえるでしょう。
『アイヌ神謡集』のカムイユカラをそっと口ずさんでみる時、自然に、神様が私達のそばにそっと戻ってきてくれるような…そんな気が私はいつもするのです。
参考文献
- 『アイヌ神謡集(1978年)』知里幸恵編訳(岩波文庫)




















![「後屈が怖くなくなった!」10年後も動ける体を作る3ヶ月プログラム「THE BASIC」修了生のリアルな声をお届け![ LIVE ]](https://i.ytimg.com/vi/tbrWFTQlhno/mqdefault.jpg)