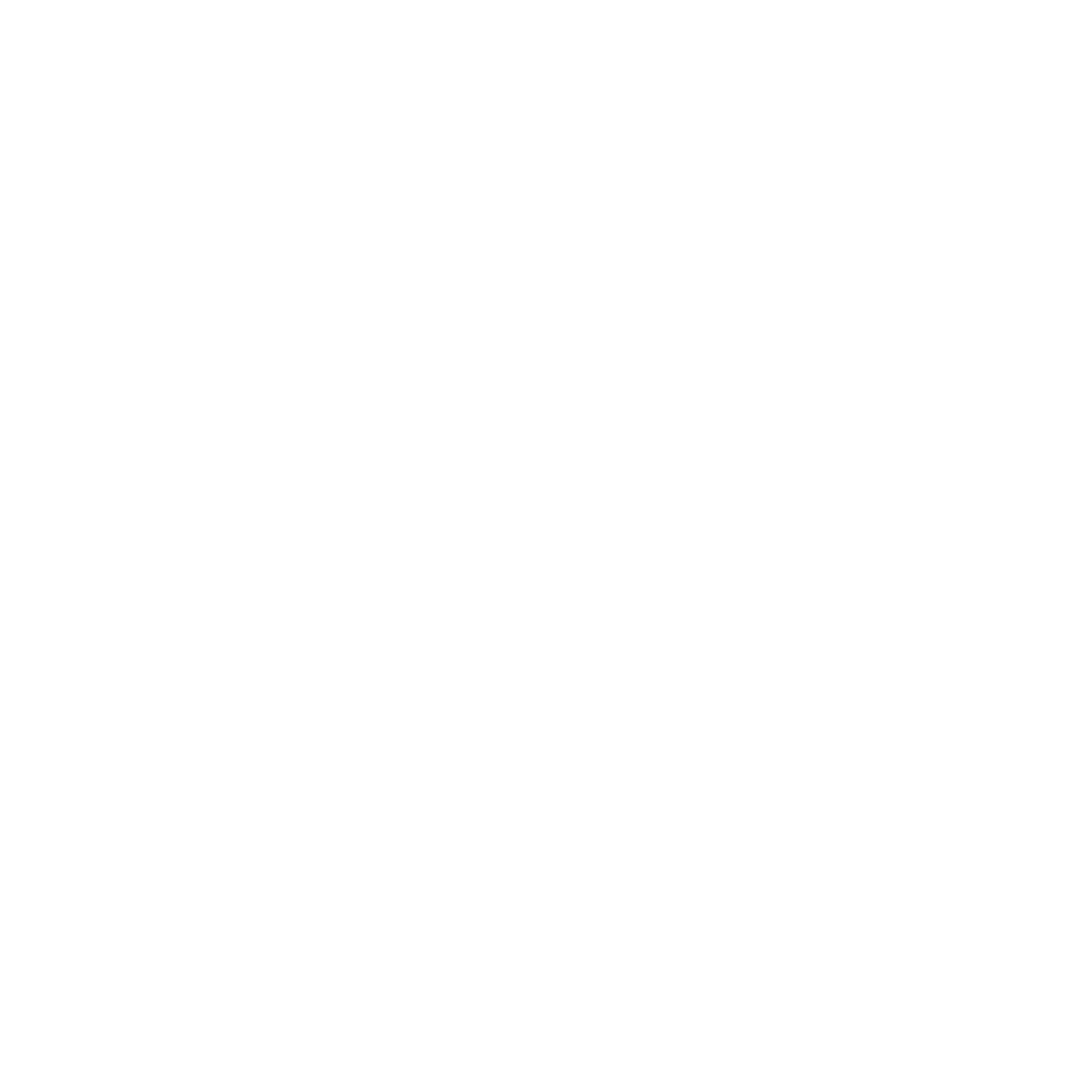こんにちは、丘紫真璃です。
今回は、ルーシー・M・ボストンの『海のたまご』を取り上げたいと思います。
ボストンはイギリスの女性児童文学作家で、代表作『グリーン・ノウのお客さま』ではカーネギー賞も受賞しています。
『グリーン・ノウ』シリーズでは、自身が住むイギリスで最も古い館を舞台にして作品を描きましたが、『海のたまご』では、コーンウォールの海を舞台にしています。
胸が痛くなるほど美しく、神秘的で、とらえどころのない海の魅力を余すところなく書き尽くしている作品、それが『海のたまご』だと言ってもよいでしょう。
そんな『海のたまご』が、ヨガにどんなつながりがあるのでしょう?
一緒にコーンウォールの海へ行って考えてみましょう!
60歳すぎから作家となったボストン
作者のルーシー・M・ボストンは、1892年生まれ。
作家として活動しはじめたのは遅く60歳過ぎてからでした。自身が住んでいた古い館を舞台に『グリーン・ノウ』という子ども達に向けた本を書き始めます。
全部で5冊ある『グリーン・ノウ』シリーズは、どれも高い水準の作品に仕上がっており、第二次世界大戦以降のイギリスの児童文学作家達に大きな影響を与えたといわれています。
『海のたまご』は、そんな彼女が1967年に描き始めた物語。
彼女はある講演で次のように述べています。
今日わたしの家は街の郊外にあります……わたしの愛するグリーン・ノウは小さくなってしまいました……もうこの家が存在するための余地がなくなってしまったのです。このことが『海のたまご』に向かってわたしが翔んでいったことにかかわりがあるかもしれません。海は相変わらずリアルで、ちぢんでしまうということはないからです。
(『海のたまご』あとがき)
批評家によっては、『海のたまご』こそ、ボストンの最高傑作だといわれるほど素晴らしい名作です。
男の子の人魚トリトン

舞台はイギリスのコーンウォールの海。主人公のトビーとジョーという2人の少年は、休暇でコーンウォールの海辺にある別荘に泊まっています。
物語は次のような美しい海の朝からはじまります。
朝早く、トビーとジョーがまどの外を見ると、塩がひいているところでした。波のない青あおとした海は、空をうつしている鏡のようになめらかで、さざなみひとつたてず、ゆっくりと岸辺からひいていきました。
なんだかふしぎな朝でした。あたりは世界じゅうの秘密をおしかくしているようにしずまりかえって、人をしあわせな気持ちにしてくれるようなおだやかな光をいっぱいにあびていました。
(『海のたまご』)
こんな美しい朝、トビーとジョーが浜辺を歩いていると、エビとりのおじさんと出会います。
おじさんは、エビつぼの中に見たこともないものがはいっていたといい、2人に見せてくれます。
それは、たまごの形をした石でした。
石はポケットにはいっていたので、なまあたたかく、大きさはシチメンチョウのたまごくらいでした。全体はみどり色で、白のすじがはいっていて、黒い斑がちっていました。
(『海のたまご』)
エビとりのおじさんによると、こんなたまごの形をした石はまず見つかることはないらしいのです。
浜辺にはいろんな形の石ころが転がっているけれども、海は完全なたまごの形をした石をこしらえたりしないものなんだそうです。
実際、トビーとジョーが浜辺を探してみても、たまごの形をした石ころは見つかりません。
2人はそんな珍しいたまごの形をした石をどうしても欲しくなって、5シリングでおじさんから買います。
少年達は、おじさんから買った海のたまごを、2人の秘密の磯のプールに入れておくことにしました。
その磯のプールは、ひき潮の時に岬にあいている自然のトンネルをくぐりぬけていった奥にあるもので、岩に囲まれている天然の海のプールなのでした。
そこにたたえられている、すんだあたたかなしずかな水は、磯だまりの中にまた磯だまりのある、すばらしい海の風景をかたちづくっていました。もも色のツルモや、宝石箱の中のビーズのように、光っている小石でかざられているそのあたりの岩棚や、ポケットのようにえぐれている潮だまりにも、水ははまっていました。
(『海のたまご』)
少年達は、天然の磯のプールの底に海のたまごを入れておきました。
すると、何日か後、海のたまごが、ただの石ころではなかったことがわかりました。磯のプールに、男の子の人魚トリトンがいたのです。
トリトンを通して海を知る

トリトンは、金髪いたずらっこらしい顔つきをしている男の子の人魚で、ばら色とエメラルド色のうろこで覆われた2股の尾をもっています。
トビーとジョーは、海のたまごから生まれたこの摩訶不思議なトリトンと友情を育んでいくことになるのですが、このトリトンとの友情を通じて、少年達は、海というものを改めて深く知っていくことになるのです。
例えば、少年達がトリトンと遊んでいる時、こんなことが書いてあります。
こうして3人は、時間をわすれてあそびほうけました。こんなゆかいななかまがいれば、海はもうよそよそしい他人ではなくなってしまいます
(『海のたまご』)
さらにトリトンと楽しく遊びたわむれて別れた後、少年達にとって、海は前とは変わって見えたと書いてあります。
ふたりにとって、海はもうつめたくも、灰色でもありませんでした。海はあたたかな砂の色で不透明でした。そしてそこここにある大岩は、海水が茶色のつやをつけたので、アザラシのように見えました。きゅうにそれまでは聞こえなかった海のざわめきが、ふたりの耳に聞こえてきました。海は、波がかろやかに、うれしげにくだける浜辺にそのいきいきとたのしげな音楽をおくってよこし、永久にその音楽をやめないとふたりにやくそくしているようでした。
(『海のたまご』)
さらに休暇最後の夜、家を抜けだした2人は、トリトンのほら貝の笛の音に誘われて、月夜の海を泳いでいくことになります。
月夜の海の神秘的な怪しさと美しさ、胸がしびれるほど素晴らしい夜の海の秘密を2人はトリトンを案内人としてのぞくことになるのですが、少年達はこうして、海というものの秘密をだんだん知っていくのです。
そして、読者もまた、少年と共に海の深い神秘を体験していきます。
五感全てで真実の姿を見る

この作品について、作者のボストンは次のように述べています。
今日では古くさいと思われるかもしれませんが、わたしは大人には、喜びについて思いおこしてもらいたい……子どもには、自分の感覚を信じて使い、直接ものごとを体験するようなはげましをあたえたいのです。耳や目や鼻を、指や足のかかと、皮膚や呼吸を使い、筋肉の動き、リズム、胸の鼓動の作りだす喜びを味わい、本能的な愛や憐み、未知のものに対する畏敬の念を知ってもらいたいのです。直接的な感覚の刺激から想像力というものは生まれるのですから……。
(『海のたまご』あとがき)
あとがきを書いている訳者の方も言っているのですが、ボストンはまさしく、『海のたまご』の中で、自身が言っていることを実現しているといってよいでしょう。
少年達は五感全てをフル活用して、海というものと向き合っていきます。
五感全てを最大限に活かして海と向き合っている少年達の姿は、ヨギーの姿とどこか重なっているような気がするのは、私だけでしょうか?
ヨギーはアーサナを行う時、ただそれらしいポーズを取るだけではないですよね。
そのアーサナを行っている時の呼吸の具合に耳を傾け、指先から足先、細胞の1つ1つに至るまで神経を張り巡らせ、心身の状態を心の目を開いてのぞいてみる、それがアーサナを行うということですよね。
つまり、ヨギーはアーサナを行っている時、自分自身をより深く見つめ、自分自身というものと深く向き合っているといえるのだと思います。
五感全てを使って、海や自分自身と向き合うということ。それは、海や自分自身の真実の姿を知ろうとしているということではないでしょうか?
お休みは日一日と少なくなっていきました。そしてとうとうあと三日しかないという日がきてしまいました。ふたりはそんなことは考えるのもいやでした。そしてこう日が少なくなってくると、どの日もきりきりまで利用しなくてはなりませんでした。でも男の子たちはよそへいきたがりませんでした。あのおなじみの入江はふたりにとって、つきることのないおどろきを味わわせることをやくそくしてくれる場所だったからです。
両親はお休みのあいだに、いろいろちがった海の景色を子どもたちに見せておきたいと思っていました。両親は、子どもたちがより多くの場所を見れば、それだけ多くのことを学ぶだろうと考えちがいをしていました。
(『海のたまご』)
両親にはいつも同じ入江に見えた入江は、少年達にとっては決して同じものではありませんでした。そこにはいつも新しい発見があったのです。
ヨガ・スートラに、真実の知とは自分自身の体験のみ知るということが書いてあります。
インドのヨガの大家は「あなたが学んだことを全て忘れよ。もう1度子どもになるのだ。そうすればその知を悟ることはたやすい。」と語りました。
五感全てを使って、海というものを感じたトビーとジョーは、真実の海を知ったのです。
そして私達も五感全てを使ってアーサナを行う時、それは真実の自分自身を発見していける第1歩になるのではないでしょうか?
『海のたまご』を読むと、潮騒の音や香り、微妙に色が変わっていくさざ波の光、海を泳ぐ時の水の冷たさや温かさ、泳いでいる時に皮膚に感じる水の感覚……海そのものを五感全てで味わい尽くすことができます。
その五感に響く美しさは、1つの大きな詩を読んでいるようだと言ってもよいかもしれません。
そんな海の神秘と魅力の詰まった『海のたまご』を、ぜひ1度手に取ってみて下さい!
ルーシー・M・ボストン著 猪熊葉子訳『海のたまご』岩波少年文庫 (1997年)




















![[ アーユルヴェーダの先にあるもの:自己肯定感 ]自分のことが好きですか?認めていますか? アーユルヴェーダ講師:福田真理](https://i.ytimg.com/vi/TF7yPuoPUVk/mqdefault.jpg)




 免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました
免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました