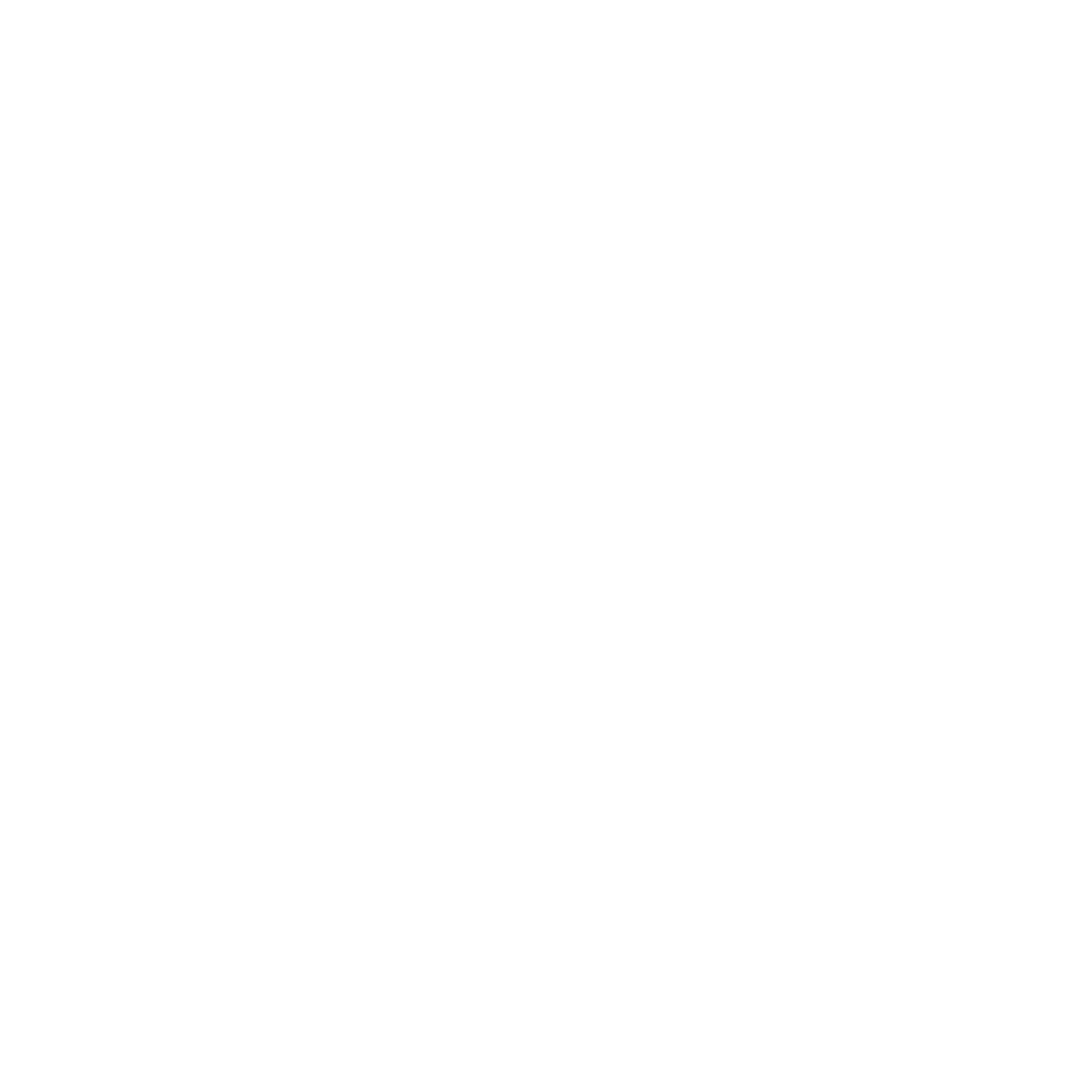皆さん、こんにちは。丘紫真璃です。
前回に引き続き、「シッダールタ」を考えていきたいと思います。
シッダールタは前半が第1部、後半が第2部と別れており、ヘッセは第1部をすぐに書きあげ、1902年に『新展望』誌で発表しています。
ところが、第2部にさしかかると、ピタリと筆が止まってしまいました。
すでに20年もインド思想を研究していたヘッセでしたが、それでもシッダールタがいかに解脱したかということを描くのは困難だったのでしょう。
あらためて修行に励み、思考を深め、3年の月日を経てようやく第2部は完成に至りました。
今回はその第2部をくわしく見ていきましょう。
シッダールタの堕落

インドのバラモンの子シッダールタは解脱を目指して修行に勤しんでいました。
全ての欲望を抑え込み、厳しい禁欲の生活を自分に強いていたのです。
しかし、いくら賢明な師に教わって修行を重ねても、真我を見出し、解脱に至ることはできませんでした。
解脱は教わってできるものではなく、自分自身で見出さねばならないものなのだと悟ったシッダールタは、自分自身で真我を見つけるため、まずは自分自身のことを深く知ることにします。
自分を抑え込むのをやめ、心の赴くままに、欲望の赴くままに生きて、シッダールタという人間をよく知ろうと決めたのです。
そうした決心をしたシッダールタがまず心惹かれたのは、美しい遊女カマーラでした。
美しい上に賢いカマーラの虜となったシッダールタは、彼女から愛というものを教わろうと決意します。
カマーラの愛人になるためには身なりを整え、カマーラに手土産を持ってこないといけません。それにはお金が必要でした。
沙門であった彼は一銭も持っていませんでしたが、カマーラの紹介で、町1番の金持ちであるカーワスワーミの下で働くことができました。
そこで、彼は商人としてお金を稼ぎ、次第に金持ちになっていきます。
ついには召使もいる屋敷も構えるようになったシッダールタは、しかし、金持ち商人の暮らしを続けるうちに、知らず知らずのうちにその生活に毒されるようになってしまいました。
沙門から、ゴータマから、バラモンなる父から学んだ多くのことは、まだながいあいだ、彼の中に残っていた。節度のある生活、思索の喜び、瞑想の時、肉体でも意識でもない自己、永遠な自我の自覚など、そういうものは彼のうちにかなり残っていたが、逐次没し去って、ほこりにおおわれてしまった。陶工の轆轤が一度動かされると、ながいあいだ回転しているが、徐々に衰え、ついには停止するように、シッダールタの魂の中でも、禁欲の車輪、思索の車輪、分別の車輪はながいあいだ回転しつづけ、依然として回転してはいたが、緩慢に、たゆたいながら回転し、静止に近づいていた。
(「シッダールタ 第2部」)
彼は愛人となったカマーラとの戯れで官能に目覚め、女を覚え、贅沢を覚え、取引を覚え、世俗の世界に沈んでいきます。
はじめこそ、世俗の世界で生きる人々をあざけりながら眺めていたシッダールタですが、次第に自分自身も世俗の世界に沈んでしまい、そんな自分に腹が立ち、腹が立つことがどんどん増えていきます。
そんな心の苦しみを紛らわすために、彼はばくちにまで手を出してしまいます。高い金を賭けてハラハラする緊張感で心の苦しみをまぎらそうとしたのです。
そうして、どんどん悪徳におぼれ、堕落していったシッダールタは、ある日、愛人カマーラが年を取り、その美しさに陰りが出来てきたことに気が付きます。
さらに、ある夜、踊り子達と酒を煽りながら過ごした後、激しい嘔吐感を覚えます。
自分自身が嫌でたまらず、耐え切れなくなったシッダールタは、とうとうこの生活を断ち切ることを決意します。
そうして、自分自身の屋敷から着の身着のままで逃げ出し、町から遠く離れた森まで逃げていきました。
オームで生まれ変わる

森をさまよいながら、シッダールタはみじめさでいっぱいになり、自分自身が心底嫌になり、こんな堕落した自分を誰かが殺してくれたらいいと思いつめます。
この苦しさから逃れるため、いっそ身投げしてしまおうと川に身をかがめた時、不思議なことが起こりました。
彼の魂のすみっこのほうから、疲れた生命の過去から、1つのひびきがきらめくように聞えた。それは1つのことば、無意識におぼつかない声で口ずさんだ1つのつづり、あらゆるバラモンの祈りの古いはじめの文句と終りの文句、「完全なもの」あるいは、「完成」というほどの意味を持つ神聖な「オーム」だった。「オーム」というひびきがシッダールタの耳に触れた瞬間、眠りこんでいた彼の精神が突然目ざめ、自分の行為の愚かさを悟った」
(「シッダールタ第2部」)
堕落しきっていたシッダールタですが、幼い頃から重ねてきた修行の成果は魂の隅っこに残っていたのでしょう。
そして、万事おしまいという瀬戸際になって、それがシッダールタの心の中によみがえってきたのです。
バラモンの子として高い教育を受けて育ったシッダールタにとって、オームという言葉は、朝の挨拶のように当たり前のように口ずさんでいたものに違いありません。
その古くからなじみのある言葉がシッダールタの心によみがえり、それが彼をよみがえらせたのです。
自分の行為の愚かさを悟って自殺を思いとどまり、疲労困憊で眠りこんだシッダールタは目覚めた時、不思議によみがえった気持ちになっていました。
ここでは空気がなんと清く美しく、なんとよく呼吸できることだろう! 自分が逃げてきたかなたでは、何もかもが香油、香料、酒、飽満、惰性のにおいがした。金持や美食家や賭博者のあの世界を、自分はどんなに憎んだことだろう! あの恐ろしい世界にあんなにながく居つづけた自分をどんなに憎んだことだろう! 自分をどんなに憎み、そこね、毒し、さいなみ、老い込ませ、悪くしたことだろう! いや、自分はもうけっして、かつて好んでしたように、シッダールタは賢いなどと思い上がることはしないだろう!
(「シッダールタ 第2部」)
シッダールタはこの時初めて、自分がバラモンとして、苦行者としてむなしく戦った自我の正体を知ります。
シッダールタはバラモンとして、苦行者として、常に優秀で、賢者でした。
シッダールタは賢いという高慢な自我が、真我への道を邪魔していたのです。
今、川でおぼれ死んだのは”シッダールタは賢い”という高慢な自我なんだ、と彼は考えます。
ここにいるのは新しく生まれ変わったシッダールタだと思った瞬間、彼の心には喜びがあふれ、子どものように朗らかに快い青空の下に立っている自分を感じて、すっかり嬉しくなってしまいました。
流れる川を朗らかに見つめた。水がこれほど快く思われたことはなかった。移りゆく水の声と比喩をこれほど強く美しく聞いたことはかつてなかった。川は何か特別なことを、彼のまだ知らない何かを、まだ彼を待っている何かを、彼に語っているように思われた。この川でシッダールタはおぼれ死のうと思った。その中で古い疲れた絶望したシッダールタはきょうおぼれ死んだ。新しいシッダールタはこの流れる水に深い愛を感じ、すぐにはここを離れまいと心ひそかに決めた。
(「シッダールタ 第2部」)
真我はいっさいの中に

川から離れまいと心に決めたシッダールタが出会ったのは、川で渡し守の仕事をしているヴァステーヴァでした。
シッダールタは、ヴァステーヴァに全てを打ち明けて心の友になり、彼に渡し守の仕事を教わりながら、共に暮らし始めます。
シッダールタは、舟をあやつってたくさんの人を渡し、稲田で働き、たきぎを集め、バナナを摘み、かいを作り、小舟を修理し、かごを編んでつつましく暮らします。
そして、時間があればヴァステーヴァと共に川のほとりに座り、川の音に耳をすませました。川の音にじっと耳をすませていると、川が多くのことを語りかけてくるような気がしたのです。
そんなある日、死の寸前にいるカマーラと、1人の男の子が川のほとりにやってきます。
カマーラが連れていたのは、シッダールタの息子でした。
カマーラは、息子をシッダールタに託して亡くなります。シッダールタに新しく息子が出来たのです。
この息子は、カマーラによって贅沢に甘やかされて育っていたため、わがままいっぱいでした。
シッダールタのつつましい渡し守の生活に、全くなじもうとせず、シッダールタに反抗ばかりしていました。
それでも、シッダールタは息子を愛さずにはいられませんでした。息子を川のそばで育て、町の全ての悪徳から守りたいと願わずにいられませんでした。
しかし、贅沢に育っていた息子は、ある夜こっそり、小舟を盗んで町へと逃げていきました。シッダールタは悲しみ、息子を追いかけますが、息子をついに見つけることはできなかったのです。
それでも、この体験でシッダールタが人々を見る目が変わりました。
今彼は前とは違った目で人間を見るようになった。前ほど賢明に、見下すようにでなく、もっとあたたかく、もっと強い関心と同情をもって見るようになった。
(「シッダールタ 第2部」)
以前は見るにも値しないと思っていたもの、子どもに対する母の盲目的な愛や、ひとりむすこに対するうぬぼれた父の盲目的な自慢や、男を求める若い女の激しい努力などを、温かい同情を持って見つめるようになったのです。
それはもう、彼にとって無縁のものではありませんでした。
それらの人々全てが、自分と兄弟のように感じました。
彼は全ての人を愛することができるようになったのです。
そしてまた、息子にもう1度会いたいと憧れを募らせる中で、かつて、自分もまた父を置いて、2度と故郷に戻らなかったことを思い出します。
父はどんな思いで2度と帰らなかった自分のことを思っていたんだろうと寂しく思ったり、息子のことに思いをはせたりしながら、川をじっと見つめていると、川の中に様々な姿が見え、川の中から様々な声が聞こえてきました。
「(流れる水の中に)父の姿、むすこの姿が流れあった。カマーラの姿も現れて、溶けた。ゴーヴィンダの姿やほかのさまざまな姿も現れ、溶けあい、みんな川になった。みんな川として目標に向って進んだ。慕いこがれつつ、願い求めつつ悩みつつ。川の声はあこがれにみちてひびき、燃える苦しみに、しずめがたい願いにみちてひびいた。目標に向かって川はひたむきに進んだ。川が急ぐのをシッダールタは見た。川は彼や彼の肉親や彼が会ったことのあるすべての人から成りたっていた。すべての波と水は急いだ。悩みながら、目標に向かって、多くの目標に向かって、滝に、湖に、早瀬に、海に向かって。そしてすべての目標に到達した。どの目標にも新しい目標が続いて生じた。水は蒸気となって、空にあがり、雨となって、空から落ちた。泉となり、小川となり、川となり、新たな目標をめざし、新たに流れた。しかし、あこがれる声は変った。その声はなおも悩みにみち、さぐりつつひびいたが、ほかの声が加わった。喜びと悩みの声、良い声と悪い声、笑う声と悲しむ声、百の声、千の声がひびいた」
(『シッダールタ 第2部』)
彼は、川から響いてくる千の声になおも深く集中して耳をすませ続けます。
もう彼は多くの声を区別することができなかった。泣く声から楽しい声を、おとなの声から子どもの声を区別することができなかった。それはみないっしょになった。あこがれの訴えと、知者の笑いとが、怒りの叫びと死にゆく人のうめき声とが、すべてが1つになった。すべてがもつれあい、結びつき、千様にからみあった。すべての声、すべての目標、すべてのあこがれ、すべての悩み、すべての快感、すべての善と悪、すべてがいっしょになったのが世界だった。すべてがいっしょになったのが現象の流れ、生命の音楽であった。シッダールタがこの川に、千のこの歌に注意ぶかく耳をすますと、悩みにも笑いにも耳をかさず、魂を何らか1つの声に結びつけず、自我をその中に投入することなく、すべてを、全体を、統一を聞くと、千の声の大きな歌はただ1つのことば、すなわちオーム、すなわち完成から成りたっていた。
(「シッダールタ 第2部」)
父の姿やむすこの姿が映っていた川に、新たな声が加わり、たくさんの声になり、百の声になり、千の声になり、そしてそれら全てが1つになりオームという1つの歌を響かせた時、シッダールタは、息子にもう1度会いたいと悩むのをやめ、運命と戦うのをやめ、微笑しました。
彼の顔には悟りの明朗さが花開いた。いかなる意志ももはやさからわない悟り、完成を知り、現象の流れ、生命の流れと一致した悟り、ともに悩み、ともに楽しみ、流れに身をゆだね、統一に帰属する悟りだった。
(「シッダールタ 第2部」)
シッダールタはついに悟りの道を開いたのです。探し求めていた真我を見出し、解脱の道を見出したのです。
シッダールタが、この後、再会したゴーヴィンダに語っているように、真我はどこか遠くにあるわけではなかったのです。
ずっとそこにあったのです。
シッダールタの中に、川の水の粒の中に、父の中に、むすこの中に、カマーラの中に、ゴーヴィンダの中に、川の渡し守ヴァステーヴァの中に、全ての人の中にもうすでにあったのです。
それは、初めからあり、ずっとそこにあったのです。
真我は全ての中にあったということに気がついた時、シッダールタは悟りを開くことができたのでした。
曇りなき眼さえ持てば、それはいつだって気がつくことができるものだったのです。
シッダールタが、再会したゴーヴィンダに自身が見出した発見について語っている部分も、素晴らしいので、ここに全て掲載したいくらいですが、それはどうぞ、本を手に取ってご自身で読んでみて下さい。
ヘッセの美しい名文でこの物語を読み返せば、きっと、新しい感慨が胸に浮かんでくることでしょう。
自分の道に思い迷った時、深く思索にふけりたくなった時、これから長くなってくる秋の夜にぜひ、「シッダールタ」を開いてみて下さい。
このコラムが、ヘッセの名作を読んでいただくきっかけになったら、とても嬉しく思います。
参考文献:『シッダールタ(昭和57年)』著ヘルマン・ヘッセ 訳高橋健二(新潮社)


















![[ アーユルヴェーダの先にあるもの:自己肯定感 ]自分のことが好きですか?認めていますか? アーユルヴェーダ講師:福田真理](https://i.ytimg.com/vi/TF7yPuoPUVk/mqdefault.jpg)




 免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました
免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました