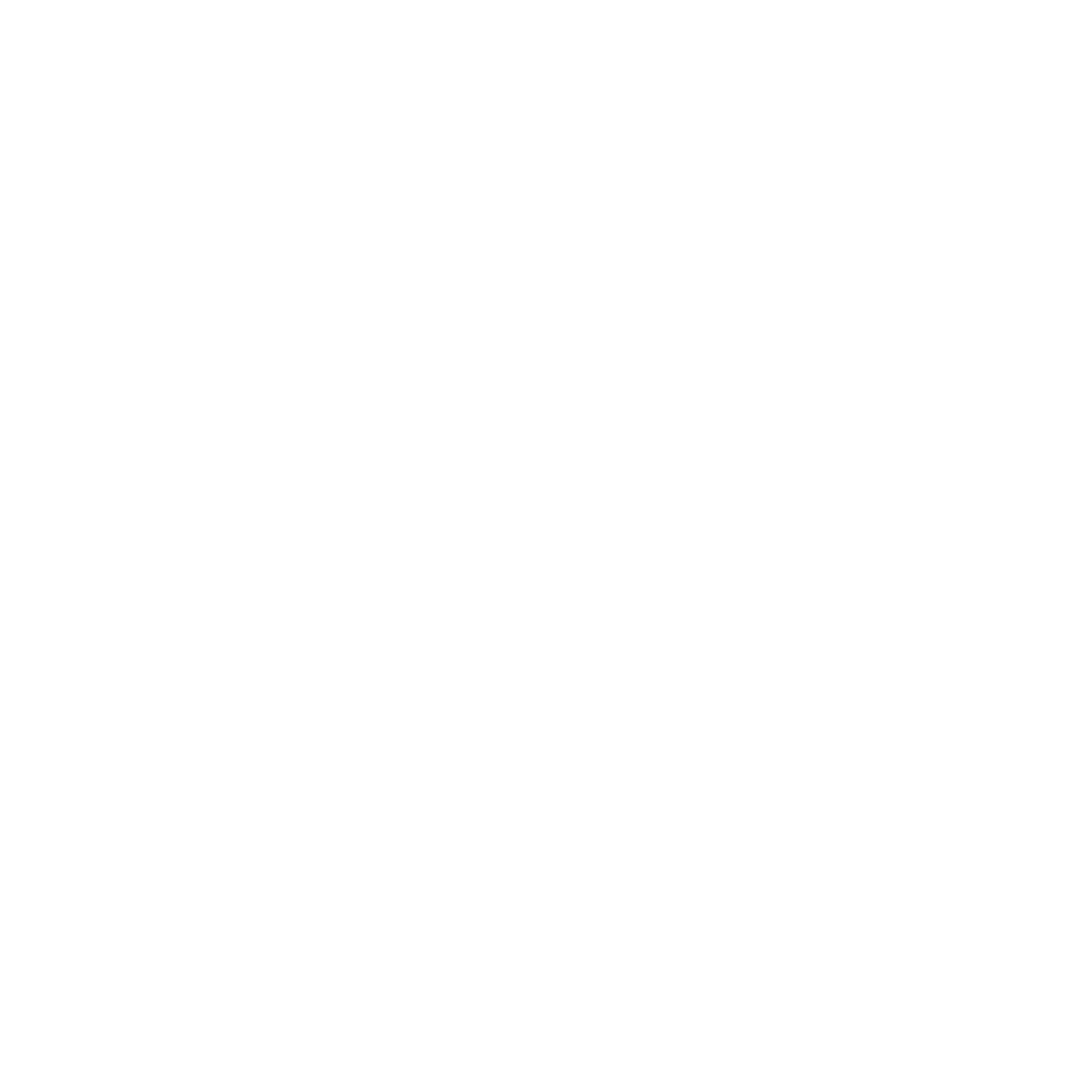みなさん、こんにちは。丘紫真璃です。
今回は、ノルウェーの女流作家マリー・ハムズンの『小さい牛追い』を取り上げたいと思います。日本では、石井桃子の名訳で紹介されたこちらの本を読んだことがある方はいらっしゃるでしょうか。作者のマリー・ハムズンは、ノーベル文学賞を受賞したクヌート・ハムズンの奥さんなのだそうです。
作者の夫であるクヌート・ハムズンは、都市の文化を否定して、素朴な自然の中で暮らす農場の暮らしにこそ価値があると考えていたので、家族そろって農場で暮らしたことがありました。マリー・ハムズンは、その時の生活をもとに、自分の息子たちをモデルにして『小さい牛追い』を描いたのです。ノルウェーの夏のまぶしさや太陽、緑広がる森や、牛たちの鈴の音がページの間から聞こえてきそうな作品です。
今回は、そんな『小さい牛追い』とヨガの関係について考えていきたいと思います。
若き母だった頃の暮らしを描いた『小さい牛追い』

作者のマリー・ハムズンは、1881年生まれ。夫は『土の恵み』という作品で、1920年にノーベル文学賞を受賞したクヌート・ハムズンです。
マリー・ハムズンは、若くて有望な女優でした。けれども、クヌート・ハムズンと出会って結婚した時に女優はやめ、農場に移り住みます。先程も書きましたが、『小さい牛追い』は、その時の農場を舞台に息子たちをモデルにして描いた小説です。
クヌート・ハムズンが、都市ではなく自然の中で暮らすことが大切だと考えていたため、農場暮らしを行っていたようですが、難しいことも多かったのでしょう。数年ほどしか続かなかったようです。それでも、農場で暮らした数年間は、マリー・ハムズンの中で特別な輝きを持って記憶の中に残っていたのではないでしょうか。だからこそ、本という形に残したのではないかと思えてなりません。
『小さい牛追い』は、その輝きが伝わってくる名作だと思います。
初めての牛追い

さて、物語の舞台は、100年ほど前のノルウェーのランゲリュード農場。主人公は、オーラとエイナールという10歳と8歳の少年です。この兄弟の妹たちも物語には登場するのですが、主に活動するのはオーラとエイナールなので、やはり主人公はこの2人の少年たちということになるでしょう。
5月。オーラとエイナールは、春になるのを楽しみにしています。春になれば、山のずっと上の方にある大きな牧場へ行き、そこではじめて牛追いの仕事をすることになっていたからです。
ふたりは、牛追いの仕事を、とてもたのしみにしていました。牛追いというのは、なかなか責任のある仕事です。お金もたくさんもうかります。というのは、小さいランゲリュード農場では、大きい、りっぱな牧場をもっていたのです。牧場は、山のずっと上の方にありましたが、それでも、まい年、大ぜいの人が遠くや近くから、牛だのヤギだのを、そこで放牧してもらうためにつれてきました。そして、秋になると、その人たちは、放牧してもらったお礼をはらうのですが、そのとき、牛追いをした子どもたちにも、百円とか二百円の心づけをしてくれない人は、ひとりもいません。げんに、教会の役僧さんなんかは、きょねん、牛追いしたふたりの子どものかたっぽに、千円もくれたほどなんですよ。でも、それは、もちろん、役僧さんとこの牛が、特別やっかいものだったというせいもありますが。
マリー・ハムズン. 訳 石井桃子. 『小さい牛追い』. 岩波少年文庫. 1995. pp, 11-12
オーラの一家は、春から夏の間、村じゅうの牛やヤギを連れて山の上の牧場で過ごします。そして、オーラとエイナールは毎日交代で、村じゅうの牛やヤギを連れて、草のたくさんある山のてっぺんへ出かけることになっているのです。そして、日が暮れるまで、たくさんの牛やヤギの見張り番をします。“羊飼い”の牛やヤギバージョンということですよね。
この作品は、そんな責任ある仕事を初めて任されたオーラとエイナールが、牛追いの仕事で四苦八苦する日常を、温かく包み込むように描いています。
……とそれだけ聞いただけでは、何がそんなに面白くて名作なのか、さっぱりわかりませんよね。
この本の一番優れた点であり、名作として長く残ることになった理由は、ズバリ、オーラとエイナールという2人の少年の心情が手に取るようにこまやかに描かれているからということにつきるでしょう。
オーラとエイナールは、異国であるノルウェーに住み、山の牧場に住んで牛追いをするような暮らしをする少年たちです。にもかかわらず、考えていることは現代の日本の子どもたちとちっとも変わりません。そして、わかる~!と思わず言いたくなるような気持ちが、たくさん描かれているのです。
例えば、一番年上のオーラは、本が大好きな少年ですが、オーラの気持ちはこんな風に描かれています。
何かあたらしい本が手にはいると、いつもこっそりどこかにかくれて、じぶんが、どこにいるかも忘れて、読みふけります。ほかの子どもたちが、そういう状態にいるオーラを呼ぼうとすれば、それはまるでべつの、遠い世界から、かれをつれもどすようなあんばいでした。不幸なことに、おとなたちもまた、オーラを呼ぶという、ふゆかいなくせをもっていました。
オーラ、少し薪をわっておくれ、オーラ、早く、水を一ぱいくんできておくれ、などというのです。オーラ、それ、オーラ、あれ、というぐあいで、一日つづきます。オーラがいちばん年上で、なんにも役にたたない、いくじなしのおとうとやいもうとをもっているばっかりに。マリー・ハムズン. 訳 石井桃子. 『小さい牛追い』. 岩波少年文庫. 1995. p,34
こんな経験、みなさんも子どもの頃にあるのではないでしょうか。夢中になって本を読んでいたりゲームをしていたり、遊んだりしている真っ最中に限って呼び出されて、勉強しろだの手伝いをしろだの言われることほど、イライラすることってありませんよね。
しかも、自分は勉強や手伝いをしているのに、弟や妹はのんきに遊んでいたら、余計に腹が立つということも年上あるあるではないでしょうか。
弟のエイナールは、本好きのオーラとは全く違った少年です。エイナールのことも実によく描けているので、またまた引用してみましょう。
あしたは、試験の日でした。そして、勉強は、あしたを最後に、ながいお休みがはじまります。
エイナールは、試験のことなんか考えません。エイナールは、まだ、A・B・Cのさきまでいっていません。そして、それさえ、たいへんにが手なのです。けれども、あした、字がまちがいなく書けようが、書けまいが、そんなこと、エイナールはかまいませんでした。エイナールは、あしたを、じぶんの生活から、きれいさっぱり追い出しました。その日だけ、とばして考えました。そして、その日のあとからくる、輝かしいお休みのことだけ考えました。マリー・ハムズン. 訳 石井桃子. 『小さい牛追い』. 岩波少年文庫. 1995. pp,35-36
これまた、とてもよくわかるという方がいらっしゃるのではないでしょうか。とりあえず、嫌なことはきれいさっぱり忘れて、試験のことなんかは心から追い出してしまうという……。
ノルウェーという異国の農場で、山や森、牛やヤギに囲まれて暮らしている昔の時代の少年の気持ちを描いているのに、現代の私たちの気持ちとなんと通じるものがあることでしょう!それだからこそ、この物語は日本でも長く読み継がれているのではないかなと、私は思いますが、みなさんはいかがでしょうか?
母は、自分と息子たちを俯瞰で見る

マリー・ハムズンは、自分の息子たちの農場暮らしをもとにこの話を描きました。つまり、この作品に出てくるオーラとエイナールのお母さんとは、おそらく作者自身のことですよね。そして驚くのは、お母さんである作者が、息子たちの気持ちをまるで手に取るようによくよくわかっているという点です。
例えば、エイナールが初めての牛追いの真っ最中に居眠りをしてポティマーという教会の役僧さんの牛を逃がしてしまった時の心情を、マリー・ハムズンはこのように書いています。
ああ、あたらしい仕事をはじめた日に、何もかもまずくいってしまうなんて! エイナールは、牛やヤギをひきつれて、得々として家へ帰るところを、これまで百ぺんも心に描いていました。もう、その夢は、おじゃんです。恥と不名誉につつまれ、そっと牛小屋に帰り、そして、あげくのはてに、ポティマーににげられたと、白状しなければならないのです。みんなは、なんというでしょう。ことによると、ポティマーは、役僧さんの家に帰ってしまったかもしれません。そうすれば、村では大さわぎがおこって、このふしまつは、そこらじゅうの大評判になってしまうのです。あわれなエイナールは、この不名誉にうちのめされました。
マリー・ハムズン. 訳 石井桃子. 『小さい牛追い』. 岩波少年文庫. 1995. p,132
自分の息子の気持ちを、まるで自分の気持ちのようにありありと描き出すことは、なかなか難しいのではないでしょうか。家族は確かに身近な存在です。けれども、私も自分の家族の気持ちがさっぱりわからないことがよくあります。だからこそ、何であんな失敗をしたんだ、こんな失敗をしたんだと責め立てたくなったりするんですよね。
でも、マリー・ハムズンは、息子であるエイナールが失敗した時の気持ちを、こんなにもよく描き出しているわけです。なぜ、ここまでありありと描き出すことができたのかといえば、それは彼女が、小説家の目で自分と息子たちを見ることができたからではないかなと思うのです。
この物語は、三人称、つまり、神の視点から描かれています。つまり、マリー・ハムズンは、ちょっと離れた神の視点から自分と息子たちを取り巻く世界を俯瞰で見ることができたのです。この俯瞰で見ることができたという点が、とても重要な点だと思います。
物事を俯瞰で見るということは、とても大切なことです。自分のことを俯瞰で見ることができる時、人は感情の波におぼれることはありません。自分の心を冷静に観察できるので、心をいつも落ち着かせていることができるのです。
息子が居眠りしている間に牛を逃がしてしまったら、もちろんマリー・ハムズンだって、母として不安になったり心配になったりするでしょう。けれども、そうして不安になったり心配になったりする自分を、彼女は一歩離れた視点から見ることができるのです。
つまり、不安や心配におぼれすぎることがないのです。
『ヨガ・スートラ』には、心がいつも落ち着いている人は、周りの物事を正しく見ることができると書かれています。
マリー・ハムズンは、いつも心を落ち着かせることができたから、息子たちの気持ちをまっすぐありのままに見つめることが出来たのでしょう。だからこそ、息子たちの心情を手に取るように描き出すことができたのです。
エイナールが居眠りして牛を逃がしてしまった時、お母さんであるマリー・ハムズンは、彼のことを叱りませんでした。牛を逃がすという大失敗をしてしまったエイナール自身が、誰よりも悔やんでいたということをとてもよくわかっていたから、それ以上責めなかったのでしょう。
物語の全編を通して、オーラとエイナールのお母さんは、息子たちのことをびっくりするほど叱りません。
オーラがエイナールをいじめた時も、エイナールが沼にハマってドロドロになったあげくに服をなくしてきた時も、ちっとも叱らないのです。それは、息子たちがどうしてそんなことをするのか、その気持ちがとてもよくわかっているからなのでしょう。
そんなお母さんだからこそ、息子たちはその日に起こった出来事を何でもよく話します。
そして、母に温かく見守られながら、つらいこともある牛追いの仕事を勇敢にこなして、たくましく成長していきます。
『小さい牛追い』の本を開くと、ノルウェーの夏の温かい太陽や牛、ヤギの放牧される緑の森、その中で生きる少年たちのはち切れそうなエネルギーをひしひしと感じます。
そうした自然や少年たちに触れながら本のページをめくっていると、毎日の生活でイライラしている時や疲れている時でも不思議と心が落ち着いてくるのです。
みなさんも、ストレスがたまった日などにぜひ『小さい牛追い』を読んでみて下さい。続編の『牛追いの冬』も合わせて読むと楽しいですよ!

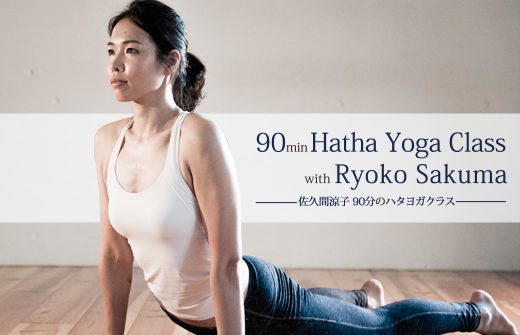


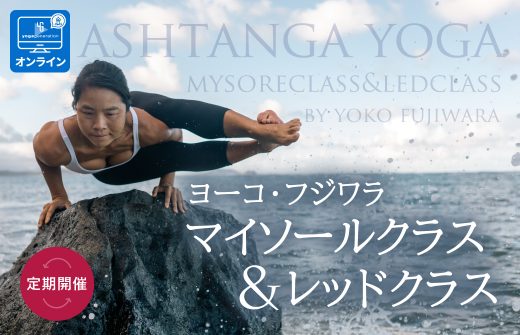

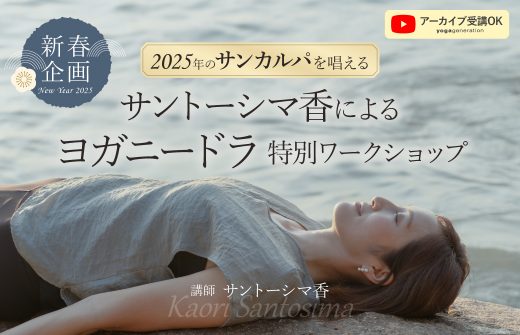

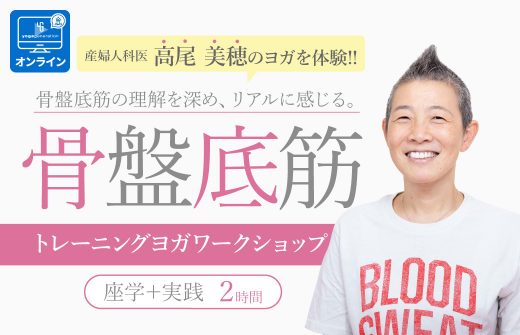












![福田真理×MIKIZO YouTube LIVE[アーユルヴェーダの先にあるもの]](https://i.ytimg.com/vi/rY5WcQmR9EI/mqdefault.jpg)

![「腰椎ヘルニア」にヨガ・ピラティスでできること。リハビリの現場では何をしている?理学療法士:間所昌嗣先生にお話しいただきました[ スポーツ医学アカデミー2025 ]](https://i.ytimg.com/vi/lc7O54fyEus/mqdefault.jpg)