※ 本記事では震災に関する内容が含まれています。このテーマに敏感な方は、無理せずご自身のペースでお読みいただければと思います。
みなさん、こんにちは。丘紫真璃です。
前回は、神戸の精神科医である安克昌医師の『心の傷を癒すということ』という本を取り上げました。今回も引き続き、この本とヨガの関係について語っていきたいと思います。
東日本大震災から、14年の歳月がたちました。あの日、テレビで見た衝撃的な光景は今も忘れることができません。大津波が、町をみるみる呑み込んでいく恐ろしい惨状を忘れられないという方は、たくさんいらっしゃることでしょう。
災害は、心に大きな傷を残します。そのことは、前回のコラムで書かせていただきました。阪神淡路大震災ばかりでなく、東日本大震災、熊本や新潟の地震、大豪雨や土砂災害、能登半島地震で災害に見舞われた方々も、どんなに大きな傷を心に受けたことかと想像すると、気が遠くなる思いです。
災害による心の傷の問題は、今も私達が直面している大きな課題だと言えます。だからこそ、今、安医師の遺したこの本を多くの方が読むべきだと、強く感じるのです。
そんなわけで、今回は、安医師がこの本に綴ったメッセージとヨガとの関係を考えていきたいと思います。
世界は傷つけるもので満ちている

心の傷の問題は、今にはじまったことではありません。人間は、古代からずっと心に傷を負い、苦しんできました。だからこそ、古代インドではヨガが発展してきたのです。ヨガの目的は、苦しみに満ちたこの世の中で心を安定させることにありました。本来、ヨガとは、苦しみの中で心を安定させるための哲学であったのです。ヨガは、約6000年前にインドで始まったと言われていますが、そんな大昔から人は傷ついていたのだということがわかります。
人間の心を傷つけるものを「心理社会的ストレッサー」というそうですが、そのことについて、安医師は次のように語っています。
私たちの住む世界は、心を傷つけるものに満ち満ちているのである。そして、阪神淡路大震災によって、被災者の「心理社会的ストレッサー」は急激に増大した。家族、教育、職業、住居、経済、医療、犯罪…。どの領域においても問題は山積みとなった。ストレッサーに直撃された人ばかりでなく、被災地に住む人全員にストレスは覆いかぶさったのである。
この被災地全体におけるストレスの高まりは、もちろんテレビカメラには映らない。それはこの地域に住む人にしか実感できない事実である。一見のどかな、あるいは活気ある風景の裏で、多くのストレスがひしめきあっているのである。安克昌. 『心の傷を癒すということ』. 作品社. 2020. p,206
それでも、神戸から離れた場所でテレビを見ている人もまた、心の痛みを感じたはずだと安医師は語ります。私の母は、当時埼玉県に住んでいましたが、神戸は故郷であり、親戚もたくさん住んでました。故郷の神戸が焼けていく惨状をテレビで目にした時、ただごとではない衝撃を受けたといいます。
心の傷を受けるのは、災害だけとは限らないですよね。交通事故や、家庭崩壊、失業や、転職による人間関係の難しさ、いじめの問題や不登校……。数え上げればきりがありません。人間は、生きているだけで心に傷を受けてしまう生き物だと、安医師も本の中で語っています。
悩みもまた傷の一種だと、安医師は言います。悩みがない人なんていませんよね。誰だって、何かしらの悩みを抱えています。その悩みが深刻になっていくと、精神病を患ってしまうこともあるのです。
精神病を患ってしまった時に、精神科医の先生方はもちろん診療をしてくださいます。けれども、精神科で処方される薬、あるいはカウンセリングで、病状を落ち着かせることはできても、心に受けた苦しみを取り除くことはできないのだと安医師は語ります。その苦しみとは、自分で向き合っていくしかないのです。
それでも、安医師はこう続けます。
もう二度と、心的外傷を受ける前のもとの自分に戻ることはできない。心的外傷から回復するために、自分は変わらざるを得ない。社会に復帰する前に、そういう新しい自分との折り合いをつけてはじめて、社会への復帰が可能になるのである。
心的外傷から回復した人に、私は一種崇高ななにかを感じる。外傷体験によって失ったものはあまりに大きく、それを取り戻すことはできない。だが、それを乗り越えてさらに多くのものを成長させてゆく姿に接した時、私は人間に対する感動と敬意の念を新たにする。安克昌. 『心の傷を癒すということ』. 作品社. 2020. p,246
どんなことでも変わってゆく

『ヨガ・スートラ』によれば、変わらないものはないといいます。たった1つ変わらないものは、プルシャという永遠のものです。その永遠のプルシャ以外の全てのものは、絶えず変わっていくというのです。
私達人間だって一秒ごとに年を取っていきます。たった一秒前の自分と今の自分とは、もう違っています。そうして、家族が変わり、環境が変わり、職業が変わり、自分自身の体力も衰え、いつか亡くなっていくわけです。人間は、絶えず変わっているのですよね。
地球は巡り、春になれば緑は芽吹き、秋には葉が落ちて枯れていきます。全ての生き物は生まれては亡くなり、また生まれては亡くなっていく。
町だって古い建物が壊され、新しい建物が建ち、そして時には災害が起きて、その姿は刻々と変わっていきます。
そう、変わらないものはないのです。全ては絶えず、変わっていくのです。
人間の心だって変わります。この世の中は、心を傷つけるもので満ち満ちているわけですから、誰だって傷つきます。でも、心はいつまでもそのまま傷ついているわけではありません。傷ついたままでいることは、できないのです。心は苦しみ、もがきながら変化していくのです。
阪神大震災が起きて、誰もが大きな傷を受けました。その傷は、並大抵のものではなかったことでしょう。災害を経験していない私なんかが語ることができないくらい、それはとても大きなものだったことは間違いありません。
でも、その傷はいつまでも、同じ状態のまま残っていることはないのです。心は苦しみながらも絶えず変わっていき、そのうち、光が見えてくることだってあるのです。
傷ついた人に寄り添う社会

その心を良い方向に変化させていくための方法が、『ヨガ・スートラ』に書かれているといってよいのではないかと思います。先程も書いた通り、ヨガとは、苦しみに満ちたこの世の中で、いかにして心を安定させることができるのかという方法を考えたものです。ですから『ヨガ・スートラ』には、苦しみ傷ついた時に、どのようにすれば心が良い方向に変わっていくのかということが、いろいろと書かれているわけです。
そして、『ヨガ・スートラ』に書かれていることと同じことを、この本で安医師が大事なメッセージとして力強く語っているのです。
例えば、『ヨガ・スートラ』には、傷ついたり不幸な人を見た時に、その人を助けることが大切だと書かれています。傷ついた人を助けることは、自分の心を救うことにつながっていくからだというのです。
それと同じことを、安医師も語っています。
症状の重くなった人は病院を訪れるけれども、その背景には、病院にこそ来ないが、災害のストレスが心の傷になった人たちが何十万人もいる。心のケアは被災者全体に必要なのであり、そのためには被災者と接する業務を行っているあらゆる機関が、心のケアについて自覚的であるべきだろう。
大げさだが、心のケアを最大限に拡張すれば、それは住民が尊重される社会を作ることになるのではないか。それは社会の「品格」にかかわる問題だと私は思った。安克昌. 『心の傷を癒すということ』. 作品社. 2020. p,69
阪神淡路大震災で被災した全ての人が、何らかの形で心に傷を負いました。その後に、日本を襲った東日本大震災をはじめ、数々の災害でどれだけの方々が心に傷を負ったのか、もはや数えきれないくらいだと思います。
そうした心に傷を負った人々を、どのように助けていくべきなのか。傷つき、もがき、立ち直れない人々に、どのように手をさしのべていくべきなのか。それを真摯に考えていくことが、私達一人一人が暮らしやすい社会を作るということにつながっていくのではないかと、安医師は語っているのです。
なぜなら、この世界は、心に傷をつけるもので満ち満ちているのですから。全ての人が、何らかの形で傷つくものなのですから。傷ついて苦しんでいる時に手をさしのべることのできる社会は、誰にとっても絶対に必要不可欠なはずです。
阪神淡路大震災によって、人工的な都市がいかに脆いものであるかということと同時に、人間とはいかに傷つきやすいものであるかということを私たちは思い知らされた。今後、日本の社会は、この人間の傷つきやすさをどう受け入れていくのだろうか。傷ついた人が心を癒すことのできる社会を選ぶのか、それとも傷ついた人を切り捨てていくきびしい社会を選ぶのか……。(略)
世界は、心的外傷に満ちている。心の傷を癒すということは、精神医学や心理学に任せてすむことではない。それは社会のあり方として、今を生きる私たち全員に問われていることなのである。安克昌. 『心の傷を癒すということ』. 作品社. 2020. pp, 258-259
30年前に安医師が全国に発したこの問いは、今の私達にもそのまま問いかけられているような気がします。そして、私はその問いに答えることができないような気がしました。傷ついた人が心を癒すことのできる社会になっていると、胸を張って天国の安医師に言うことは、私にはとてもできません。
暗いニュースがあふれ、貧困家庭も増え、心を傷つけるものはますます増えている気がします。当時と違い、SNSが急速に普及し、匿名でお互いを傷つけあうことも増えました。
でも、他方で安医師の意思を受け継いで、心の傷の問題と向き合っている方々もいらっしゃいますし、様々な取り組みも行われていると思います。
そんな社会のことに考えを巡らせたとき、今すべきことは、傷ついた方や失敗した方、立ち直れないでもがいでいる方々を傷つけたり批判したりすることではなく、お互いが受けている傷をもっと理解しようと努力することなのかなと思いました。
『心の傷を癒すということ』の本をめくっていくと、安医師が、深く傷ついている方や、なかなか立ち直れない方に、ものすごく温かいまなざしを注いでいるということを、とても強く感じました。全ての傷ついた方々が、きっと回復することを信じて寄り添いつづけた安医師の姿が目に浮かぶようでした。
読むのが辛い方もいらっしゃるでしょう。でも、もし、読んでみようかなと思ったら、ぜひ、手に取ってみて下さい。

![Dr.マヘシュ直接指導![症状別]ヨガセラピー体験クラス](https://shop.yoga-gene.com/wp-content/uploads/2024/11/mahesh90-top-800x515_new-520x335.jpg)

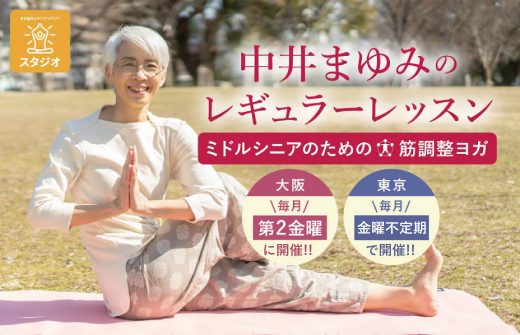


![\安全な前屈とは?/本日、オハナスマイル祐天寺では、佐久間涼子先生による「THE BASIC」が開催されていました。今日のテーマは「筋の柔軟力」柔軟性と聞いて一番に想像するのは前屈かもしれません。でも、皆さん、解剖学的に安全な前屈のやり方、ご存知でしょうか?「股関節から曲げる」「背骨を一つ一つ意識しながら曲げる」など、様々な方法がありますよね。でも、その根拠は何なのでしょうか?ヨガ指導歴20年・鍼灸師でもある涼子先生のレクチャーとアジャストで、みなさんの前屈は一気に深まりましたね・・・!体って、本当に素直。正しいやり方をすると、その通りに反応する。そんな体の奥深さに触れた一日でした!涼子先生、皆さん、お疲れ様でした^^年内は残すところあと1回。どうぞ、よろしくお願いいたします。今月、涼子先生の「ハタヨガクラス」がオンラインと東京・対面で開催されます。ぜひ、涼子先生のヨガを体験してみてくださいね。\筋トレ × ヴィンヤサ/ヨガ講師・鍼灸師:佐久間涼子「ハタヨガ90分クラス」<オンライン>12月16日(火)9:00-10:30<東京・対面>12月25日(金)10:30-12:00[検索]ヨガジェネ 佐久間涼子#ヨガ#筋トレ#ダイエット](https://www.yoga-gene.com/wp-content/themes/yogageneration/assets/images/common/xtransparent-1x1.gif.pagespeed.ic.ZvIVnS_92W.png)



