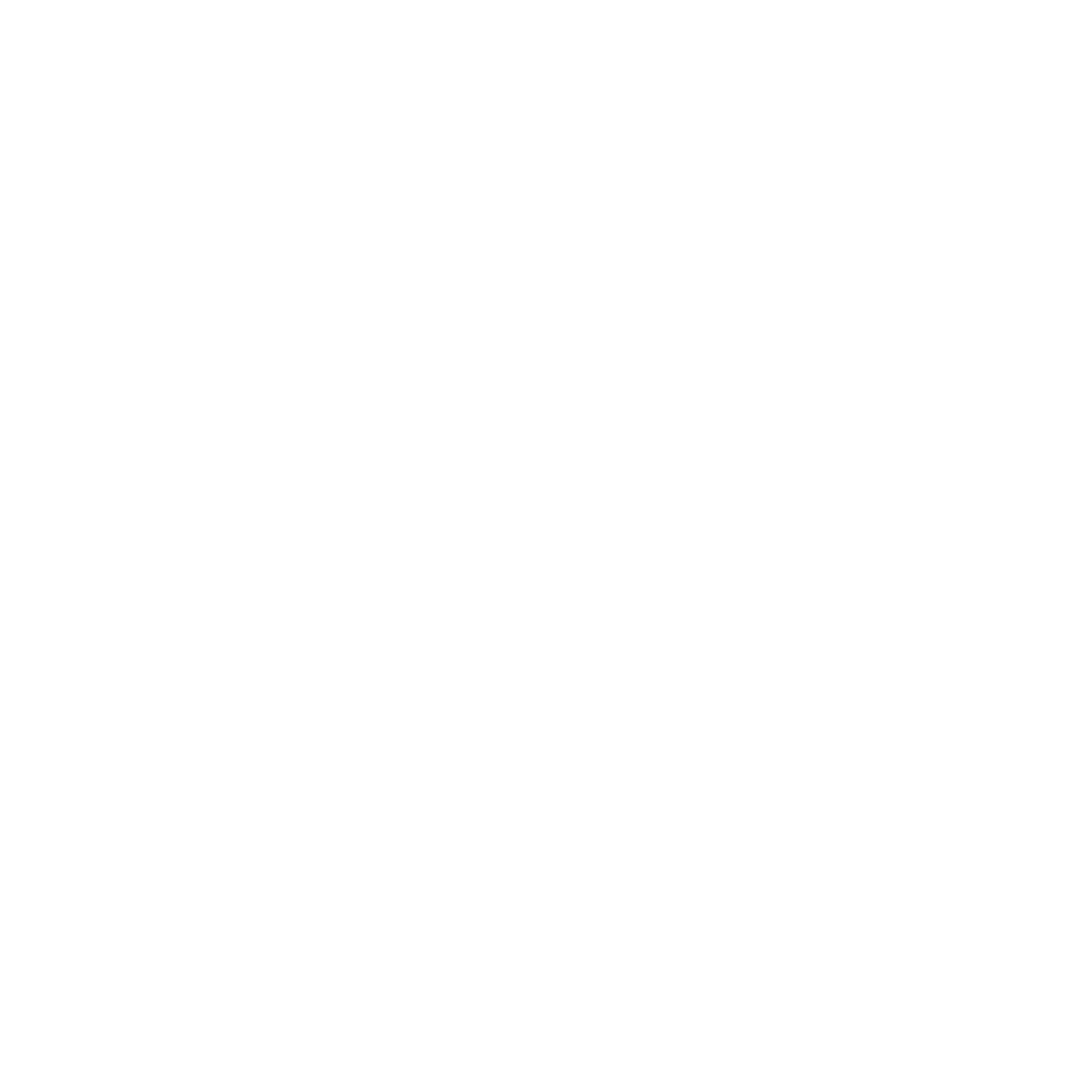みなさん、こんにちは。丘紫真璃です。
今回は、イギリスの作家であるメアリー・ノートンの『床下の小人たち』を紹介したいと思います。
第二次世界大戦後の1952年にイギリスで発表されたこの本は、カーネギー賞にも輝きました。スタジオジブリがこの作品をもとに、『借りぐらしのアリエッティ』というアニメ映画を製作したので、ご存じの方も多いかもしれません。
人間の家の床下などにひっそりと住みついて、人間の物を借りて暮らしている借りぐらしの小人たち……。魔法の力などの特別な力を何も持たない小人たちですから、人間よりもはるかにか弱い存在で、危険もたくさんあります。
この本は、小人たちにハラハラさせられる冒険話が5作に渡るシリーズになっているのですが、今回は、第1作目の『床下の小人たち』とヨガの関係について考えていきたいと思います。
安住の地を求めて転々と

著者のメアリー・ノートンは、1903年にイギリスのロンドンで生まれました。2歳の時にベドフォード州のレイトンバザードに移り住み、学齢期まで過ごします。この地が、借りぐらしの小人たちの舞台になりました。
幼いメアリーはひどい近眼で、遠くが見えない状態が当たり前だったので、自分にメガネが必要な状態だということに気がつかなかったそうです。近眼ですから遠い景色は見えず、近くの草花ばかりがよく見えたといいます。そして、近くの草や花、石などを見つめているうちに、こうした場所に小人たちが生きていたとしたらどんな暮らしをしているんだろう?と想像していたそうです。
学校に上がる年齢になって近眼だということが発覚し、メガネをかけるようになったメアリーの生活は急に忙しくなり、小人たちのことは次第に忘れていきました。
大人になってロンドンに出て女優になったメアリーは、1927年に船会社の経営者であるロバート・ノートンと結婚し、ポルトガルに住むようになります。ところが、1929年の世界恐慌で夫の会社は倒産。メアリーは、4人の子どもを連れてロンドンに帰ります。
その後は、ロンドンで役所勤めをしていたそうですが、第二次世界大戦によりドイツの脅威が増してきたため、子どもたちを連れてアメリカに渡りました。その時、子どもたちを養うお金を稼ぐために文筆業をするようになります。
同時期に、メアリーは様々な物語を作っては、子どもたちに話して聞かせていました。その頃に書かれたのが、『床下の小人たち』だったのです。
第二次世界大戦後も各地を転々として大変な生活を送っていたようですが、そうしたメアリーの人生は、安住の地を求めて様々な場所を冒険しながら転々とする小人たちの物語とどこか重なります。
全5作の小人シリーズをはじめ、数々のファンタジーを遺したメアリー・ノートンは、戦後のイギリス児童文学の先駆者として有名になりました。
人間の物を借りて暮らす、借りぐらしの小人たち

物語の舞台は、イギリスの田舎にある古い大きなお屋敷です。お屋敷には、寝たきりのソフィ大おばさんと料理人のドライヴァおばさん、庭師のクランプファールだけが暮らしています。現在は、ソフィ大おばさんの親戚の男の子も療養のために、ここで暮らしていました。
そんな静かなお屋敷の床下に、借りぐらしの小人の家族が住んでいたのです。お父さんのポッドとお母さんのホミリー、それに、娘のアリエッティの3人です。
お父さんのポッドが、ちょくちょく人間の住む部屋へ上がっていき、人間に見られないように、こっそりと、いろんな物を「借りて」くるのです。安全ピンや帽子ピン、鉛筆やマッチ、ゆびぬき、毛糸などです。
人間は、借りぐらしの小人のことを知りませんから、安全ピンや帽子ピンがちょっとくらいなくなったって、全然気がつきません。たとえ、なくなったことに気がついたとしても、「確かに買ったはずなのに、なんでなくなっちゃったんだろう?」と首をかしげて、また新しいものを買ってくるだけなのです。
そんなわけで、小人たちは、ありとあらゆる人間のものを借りてきて、なかなか豊かにくらしていました。アリエッティの家族の居間を、ちょっとのぞいてみましょう。
壁紙には、紙くずかごからもってきた古い手紙がつかってありましたが、ホミリーは、それを横につかって、かいた字が、床から天井へと、たてに縞になるようにはってありました。その壁には、まだ若いころのヴィクトリア女王の肖像画で、色だけちがうのが、いくつか、かけてありました。それは郵便切手なのですが、何年かまえに、ポッドが、朝の間の机のうえの切手箱から借りてきたものなのです。うるしぬりの宝石箱も一つおいてありました。内がわは、ふっくらとつめものがしてあって、ふたはあいたままになっていましたが、それは長いすにつかっているのでした。それから、あのべんりでありがたいもの……マッチ箱でつくったたんすもありました。
メアリー・ノートン. 訳 林容吉. 『床下の小人たち』. 岩波少年文庫. 2004. pp, 27-28
けれどもアリエッティは、いくら綺麗な居間があったってちっとも楽しくありませんでした。というのは、人間の部屋は危険でいっぱいだからという理由で、アリエッティは外に出してもらえなかったのです。アリエッティたちの暮らす床下の家には、一か所だけ外につながる格子窓がありました。アリエッティは、その窓から見える緑の野原にあこがれ、一度でいいからお日さまの下に立ってみたいといつも願っていたのです。
そんなある日、アリエッティに、ついに外に出るチャンスが訪れます。お父さんと一緒に人間の部屋へ行き、物を借りてくる手伝いをすることになったのです。
床下の家から出たアリエッティは、家の外に広がる緑の野原に夢中になり、お日さまの下に一人で飛び出していってしまいます。
そこでアリエッティは、1人の男の子と出会いました。この屋敷で療養している男の子です。
本当ならアリエッティは、その男の子に姿を見られたらいけないはずでした。というのは、人間に姿を見られるなというのが、借りぐらしの掟だったからです。それなのに、アリエッティは男の子に姿を見られたどころか、おしゃべりまでしてしまったのですから大変です。
そして、この男の子がきっかけとなり、一家は床下の家をはなれて危険いっぱいの野原へと出ていかなければならないピンチに陥ってしまうのですが、そこまでくわしく書くのはやめましょう。気になる方は、ぜひ、読んでみて下さい。
私たちは、そろそろ、この物語の何がヨガと関係があるのか考えていくことにいたしましょう。
人間は借りぐらしの小人のために存在する!?

今回、私が注目したいのは、アリエッティが男の子と出会った時に交わす会話です。
男の子はもちろん、アリエッティみたいな小人は見たことがありませんでした。でも、アリエッティの方でも、そうたくさんの人間を見たことはなかったのです。アリエッティが見たことのある人間は、この屋敷に住んでいるソフィ大おばさんと料理人、庭師と男の子だけ。だから、世界に存在する人間は、この4人くらいだろうと思っていました。
そのため、アリエッティは、こんな風に男の子に言います。
「まさか、あなたの大きさの人が、たくさんいるとでも思ってるんじゃないでしょうね?」
メアリー・ノートン. 訳 林容吉. 『床下の小人たち』. 岩波少年文庫. 2004. p,114
男の子は、自分みたいな人間はとてもとてもたくさんいるのだという話をアリエッティにしてやります。さらに、「借りぐらし」なんて言い方をしているけれども、小人のやっていることは、人間から物を盗んでいるということになるのではないかと指摘しました。すると、アリエッティはすごくわらって、こんな驚きの発言をしたのです。
「人間ってものは、借りぐらしやのためにあるのよ!」
メアリー・ノートン. 訳 林容吉. 『床下の小人たち』. 岩波少年文庫. 2004. p,123
人間は借りぐらしの小人のために存在しているんだから、借りぐらしの小人が人間からいろんな物を借りるのはごく当たり前のことで、悪いことは少しもないというアリエッティの発言に、男の子は心底驚きます。そして、私も驚いてしまいました。
人間が借りぐらしの小人のために存在するという考え方は、普通の人間にはなかなかない発想で、面白いですよね。
この物語を書いたメアリー・ノートンだって人間なのに、なぜこんな発想ができたのかというと、それは彼女がこの小人たちの物語を書くにあたって、すっかり小人そのものになりきっていたからだと思います。借りぐらしの小人の視点に立って、この物語を書いていたからこそ、このような発言を書くことができたのでしょう。
自分とは違う誰かの視点に立って考えるということは、物語を書く時だけでなく、人間関係においても大切な考え方だと思います。私たちは一人として同じ考え方ではありません。みんなそれぞれ、環境も、立場も、価値観も違います。そうした違う思考回路を持ち、違う価値観を持つ相手のことを知ろうとし、相手の視点に立って物事を見ようとする力がなければ、人間関係だって決してうまくいかないのではないでしょうか。
そして、相手の視点に立つということは、自分の持っている常識に縛られていては、決してできないことだと思うのです。自分の常識から自由になって相手と向き合うことで、相手の視点に立つことができるようになるのではないでしょうか。
思いこみや決めつけ、常識といった縛りから自由になるということは、ヨガでもとても大切だと言われていることです。思いこみや決めつけ、常識……自分が当たり前だと思いこんでいるものをどれだけ捨てて、柔軟な考え方ができるかどうかということを、ヨギーは常に問われているのです。
小人たちの物語を生み出したメアリー・ノートンは、まさしく、人間という縛りから自由になって小人になりきることのできた自由な発想の持ち主だということができるでしょう。
訳者の林容吉は、この本のあとがきに、このように書いています。
過度に人間に依存したために結局は流浪するはめになる小人一家の運命は、一時は賛美されていた文明の進歩が核戦争や自然崩壊など様々な災害を引き起こし、自らの首を絞める結果になってしまった人間の状況の写しともいえそうです。
メアリー・ノートン. 訳 林容吉. 『床下の小人たち』. 岩波少年文庫. 2004. p,268
そんな小人たちが、安住の地を求めて、危険でいっぱいの野原を渡り、やかんで川を下り、ついには空を飛ぶ冒険の物語は、5作に渡るシリーズで楽しめます。
純粋に物語として楽しめますので、ぜひ読んでみて下さいね!
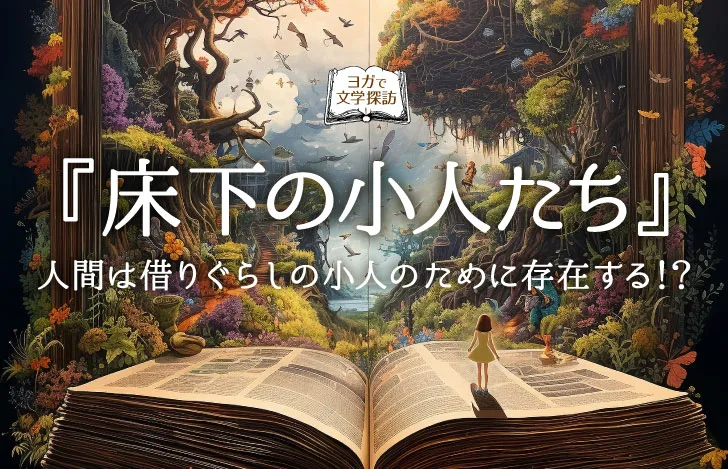
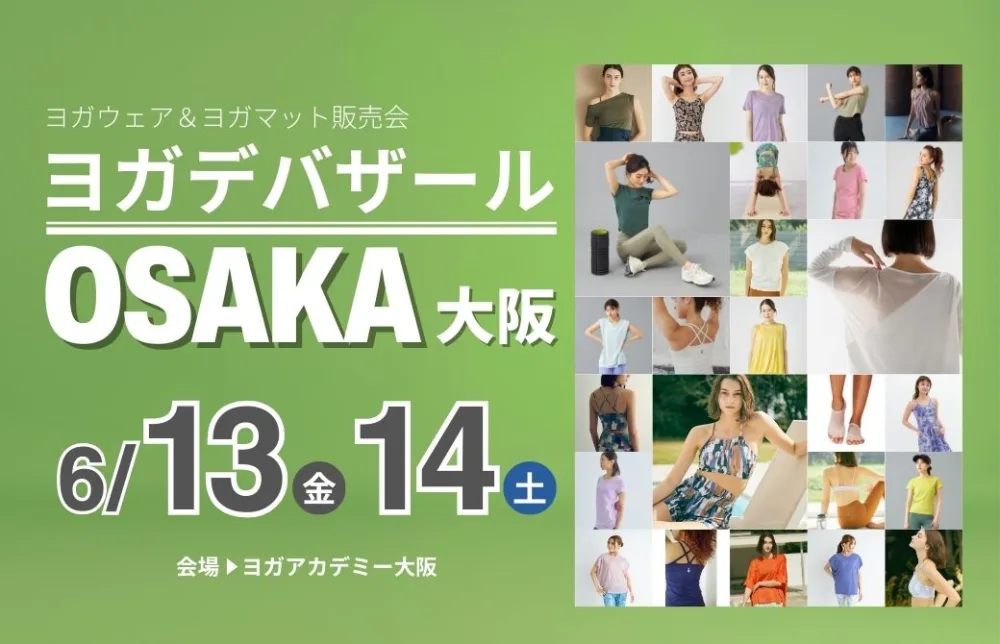

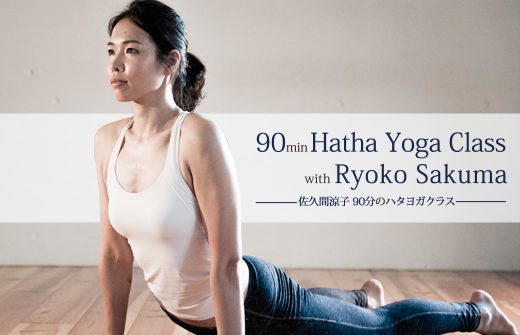

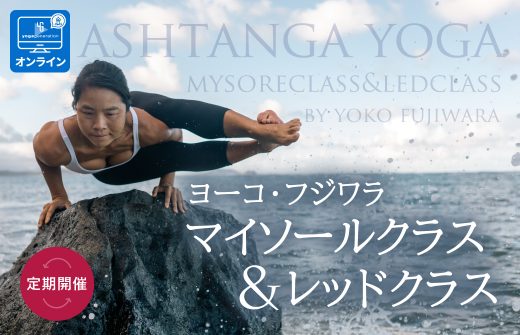

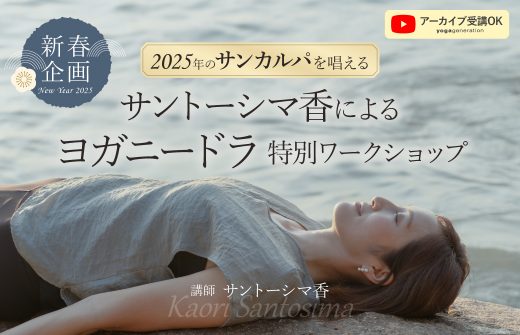

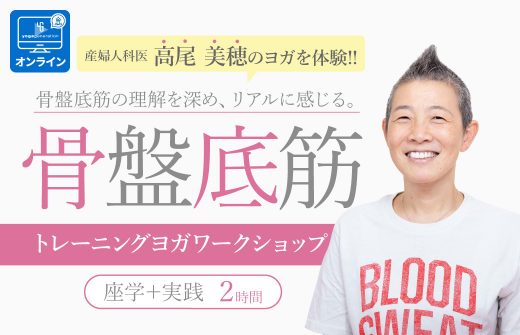


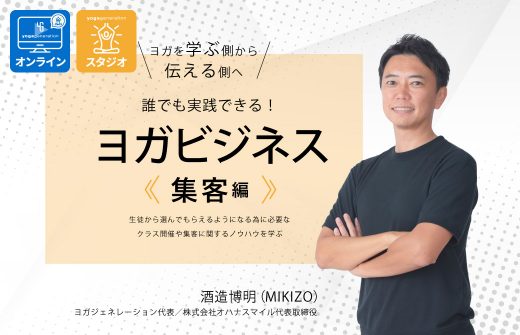




![[ アーユルヴェーダの先にあるもの:自己肯定感 ]自分のことが好きですか?認めていますか? アーユルヴェーダ講師:福田真理](https://i.ytimg.com/vi/TF7yPuoPUVk/mqdefault.jpg)




 免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました
免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました