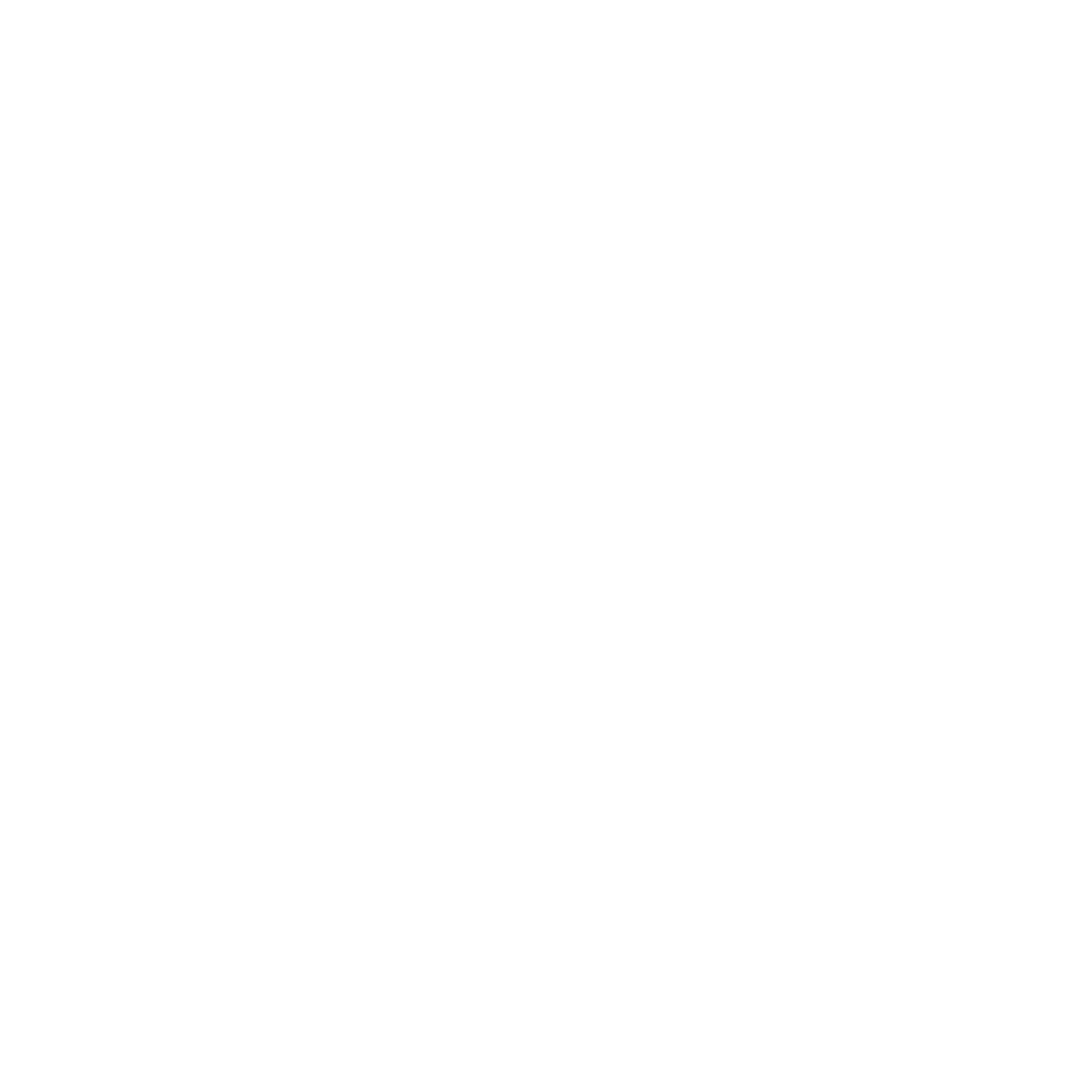記事の項目 [閉じる]
ヨガの練習は、八支則と呼ばれる8つの手順で行われます。
『ヨガ・スートラ』に書かれた八支則は、現代でも世界中の人々がヨガの実践方法として行なっており、この8つの手順は、自分自身に到達するための道でもあります。
今回は、八支則を学びながら、ヨガ的自分探しの旅を深めていきましょう。
自分に出会うための道:八支則とは

八支則は、教典『ヨガ・スートラ』の2章と3章に書かれた古典ヨガの実践方法です。
1番目と2番目のヤマとニヤマは、日常で気をつけるべき心得や道徳に近い教えが多く含まれており、アーサナではポーズ、プラーナーヤーマでは呼吸の制御、プラティヤーハーラでは感覚を制御し、最後の3段階は瞑想を行います。
- ヤマ(制戒):社会的な禁止事項
- ニヤマ(内制):自分に対する制御
- アーサナ(座法):安定した座り方
- プラーナーヤーマ(調気法):呼吸でプラーナ(気)をコントロール
- プラティヤーハーラ(制感):外界から受ける感覚を断つ
- ダーラナ(凝念):意識を一点に集中
- ディヤーナ(静慮):ダーラナで一点だった対象を広げる
- サマーディ(三昧): 心が停止した状態
この8つの段階は、1番目から順番に行うのが良いとされており、最終的に瞑想が深まった結果、プルシャ(真我)と呼ばれる自分の最も深い真実に出会うことができると考えられています。
現代の多くのヨガでは、アーサナを中心に行われることが多いと思いますが、だからといって八支則が忘れられたわけではありません。
アーサナの練習を行いながら自分を大切にすること(ヤマの1つアヒムサー)を学んだり、毎日繰り返し行う練習が、ニヤマのタパス(苦行・修行)に繋がったりします。また、アーサナを練習すると同時に必ず呼吸を意識することでプラーナーヤーマの学びも深まり、自ずと瞑想の準備が整います。
様々なヨガの流派がありますが、多くのヨガでは、八支則の教えを自然と取り入れながら実践しているのではないでしょうか。
自分を知るための旅

ヨガを練習するということは、自分を探す旅に出るようなものです。しかし、旅といっても外の世界に出かけるわけではありません。自分の内側に広がる大きな世界に気がつくことが、ヨガの旅です。
自分の本質が、自分の最も内側の中心にあるのであれば、ヨガの旅のスタート地点は、外表的な自分と向き合い、手放すことからしなくてはいけません。そのために、ヨガでは執着や束縛を弱めるための実践を行います。
八支則で外側から執着を手放していく手順
最初に向き合うことは、自分自身と外の世界との関係性です。多くの人は、自分に向き合おうと思っても、意識が外に向いてしまっています。
例えば、アーサナの練習を行なっていて自分の練習に集中したいのに、隣の人にどう見られているのかが気になっていたら集中できませんね。だから、最初に向き合うのは、社会生活の中での自分です。
八支則のひとつ目のヤマでは、他者と自分との間の確執が薄れていきます。
例えば、人間関係においてエゴが強く、自分の利益のために他者を平気で傷つけたり、人のものを奪ってしまったりする人は、常に報復を恐れています。自分が他者を傷つけるということは、同時に、自分が他者に傷つけられるターゲットになります。それでは落ち着いて自分探しの旅もできませんね。アヒムサー(人を傷つけないこと)やアステイヤ(盗まないこと)を実践することで、この世界は戦場ではなく、安心できる場所になります。https://www.yoga-gene.com/post-18317/
ニヤマでも道徳的な教えが続きますが、もう少し自分に向き合い、自分の日常の習慣を変えていきます。シャウチャ(清浄)によって毎日自分自身を清め、タパス(修行・苦行)の習慣を持つことによって、自分のヨガの旅を進み続ける意志の強さを育てます。
ニヤマは、ヨガを練習する人であれば、誰もが継続して志したい教えが含まれています。
ヤマとニヤマの実践が身につくことで、毎日の生活における外からの妨害がなくなります。外の世界とのしがらみを手放したら、次は自分自身の身体に向き合います。
自分の体に向き合いながら深い自分へと進む
アーサナ(体位法)では、しっかりと自分自身の身体に向き合います。
誰もが「私」をイメージするときに、自分の顔や体といった物質的な姿を思い浮かべるはずです。しかし、私たちの本質は体にはありません。
まずは、いったん体に意識を向け、自分の体のことを知ります。体に不調がある場合には、そこに意識が向きがちなので、アーサナによって不快感を弱めていきます。このように、アーサナの練習で自分の体を俯瞰することによって体への固執が少しずつ弱まり、さらに奥にあるエネルギーの流れも感じやすくなります。
内側のエネルギーに意識が向き始めたら、プラーナーヤーマ(調気法)の練習です。
体内のエネルギーの流れを、呼吸を使って制御していきます。自分の内側を流れるプラーナを感じてくると、そこに意識が集中し、外の世界への意識が弱まっていきます。
完全に自分の内側に意識が留まった状態のことを、プラティヤーハーラ(制感)と呼びます。これは、瞑想への入り口の段階です。https://youtu.be/BVQzGQurlds?si=4judTDmwlsI6jndh
最後に手放すのは自分の心
外の世界との繋がりが手放された時、頭で考える思考も自然と弱まっていきます。日常的な私たちの思考は、常に外の世界から得た情報を元に生み出されています。自分の感覚器官から得られる情報を手放した時には、思考が働く必要もなくなってきます。
雑念が消えた状態を、ヨガではダーラナ(集中)と呼びます。また、その瞑想状態が深まるとディヤーナ(静慮)へと続きます。すると、私たちは、「心」や「思考」さえも本当の自分ではないことに気がついてきます。頭で考えてきた自分像を手放した時に初めて、内側に宿る自分の本質に気がつくことができます。今まで「これが私」と思い込んでいたエゴを手放した時に、サマーディ(三昧)と呼ばれる段階が訪れます。
ダーラナ・ディヤーナ・サマーディの3つの瞑想状態は自然な流れで訪れ、いつの間にか到達しています。この3つは切り離すことができないため、『ヨガ・スートラ』では3つを合わせてサンヤマ(綜制)と呼びます。
今の自分の段階を意識しながらヨガの練習を行う

多くの人は、アーサナや瞑想を練習の中心においていると思いますが、ヨガのどんな練習を行なっている時にも、八支則を意識しながら練習してみましょう。
ヤマとニヤマができていないから、アーサナに進めないわけではありません。アーサナの練習をしながらでも、その中に八支則を取り入れることはできます。
例えば、アーサナの練習で呼吸と体の伸びが気持ちよく、日頃のストレスを忘れてしまっていると感じた時には、ニヤマのなかのサントーシャ(知足)の状態かもしれません。
ちょっと難しいアーサナに挑戦している時でも、均一で長い呼吸を意識できていれば、プラーナーヤーマ(調気法)の練習を兼ね備えてると考えられます。
自分の呼吸に没頭しすぎて、先生の声さえも聞こえなくなっていれば、それはプラティヤーハーラ(制感)からダーラナ(集中)の状態に入っているかもしれません。
アーサナの練習ひとつとっても、ポーズの形だけではなく、内側で起こっている自分の変化に気が付きやすくなりそうですね。

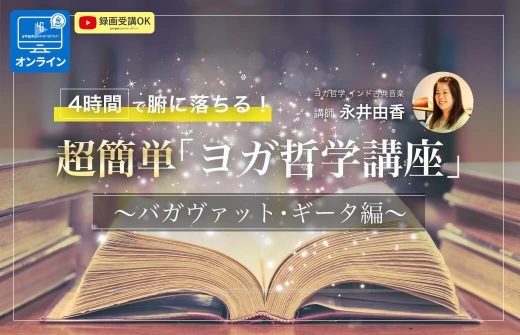
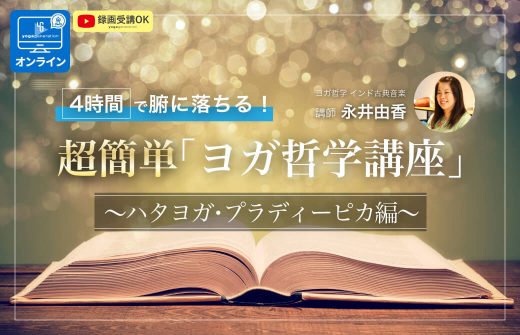

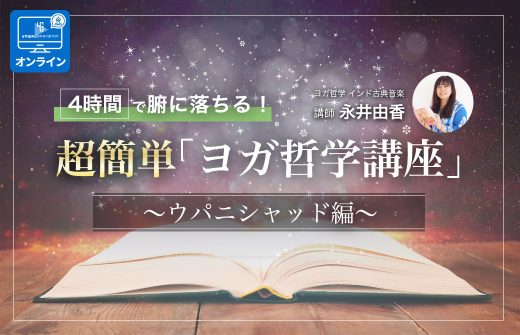
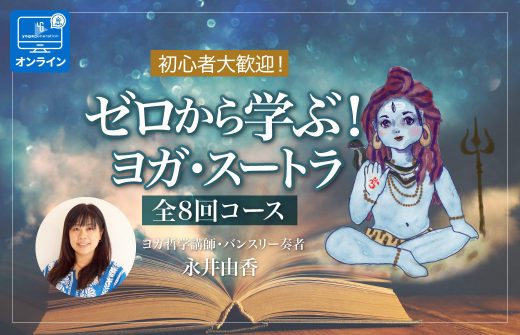

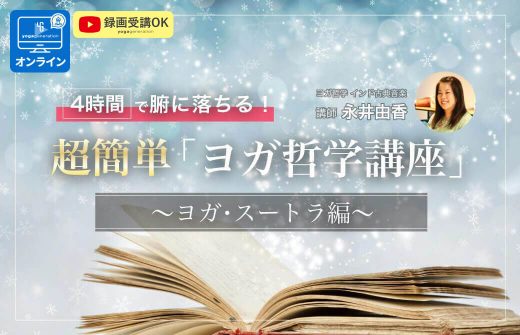
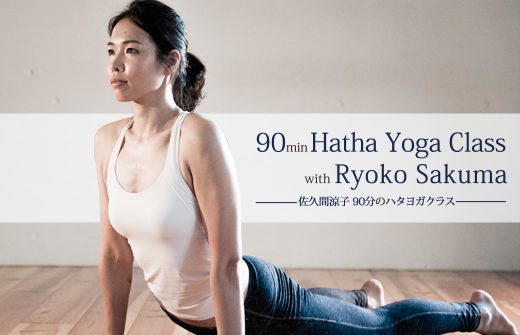

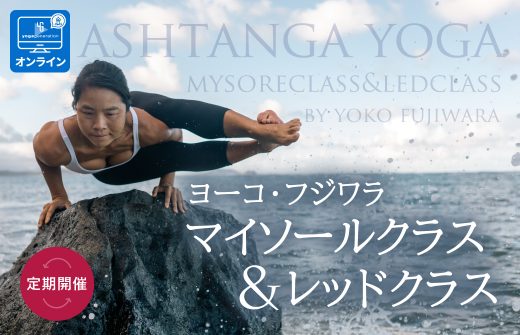

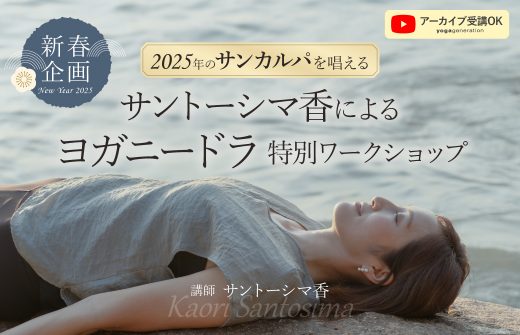

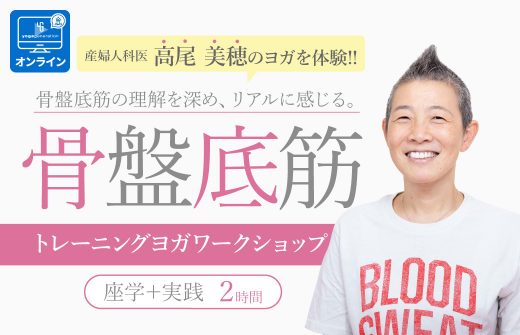











![福田真理×MIKIZO YouTube LIVE[アーユルヴェーダの先にあるもの]](https://i.ytimg.com/vi/rY5WcQmR9EI/mqdefault.jpg)

![「腰椎ヘルニア」にヨガ・ピラティスでできること。リハビリの現場では何をしている?理学療法士:間所昌嗣先生にお話しいただきました[ スポーツ医学アカデミー2025 ]](https://i.ytimg.com/vi/lc7O54fyEus/mqdefault.jpg)